中小企業診断士一次試験合格している方は、二次試験に専念もしくは、二次試験の受験権利をもう1年伸ばすために一次試験の再合格を目指すの2パターンいらっしゃいます。
どちらのパターンも経験した筆者が考える一番のおススメパターンを明確化したうえで、どのような勉強スケジュールにしていけばよいのかについてお伝えします。
中小企業診断士一次試験保険受験の是非
中小企業診断士一次試験を前年度に合格している場合、その翌年度は一次試験受験を免除されます。
免除権利はあるものの、一次試験の受験が可能です。合格すれば、中小企業診断士二次試験に不合格であっても、その翌年度の二次試験の受験権利を得ることができます。このことを、保険受験と呼んでいる人もいるようです。
保険受験によって中小企業診断士一次試験に合格できれば、その翌年度の二次試験の受験権利を確保でき、一見リスクヘッジになっているように見えます。しかし、一次試験の勉強を並行しなければならず、感覚的に3分の1程度の労力を費やす必要があります。
この3分の1をわざわざ中小企業診断士一次試験の勉強に費やすぐらいなら、二次試験の勉強時間に全てをあてた方が合格への確度は高まると筆者は断言します。
中小企業診断士二次試験に勉強時間の全てを捧ぐべき理由
皆さんも耳にされたことがあると思いますが、勉強の取り組み方として中小企業診断士一次試験は量、二次試験は質と言われることが多いです。
二次試験においても解き方を学ぶパートは、確かに「質」を重視すべなのは筆者も同感です。それは、中小企業診断士二次試験が求められているものがどんなもので、それを体現するために本質を突き止めることが一番大事だからです。
量も質もどっちも必要
しかし、「学ぶ」と「できる」には大きな乖離が生まれます。そのため一部のとても優秀な方を除いて、働きながら独学で合格を目指されている普通のサラリーマンであれば、どうしても量をこなす必要が出てきます。80分という短時間で、どのような作業をしていくことが一番効率的なのかを探るには、どうしても量が必要となるからです。
筆者が言う量とは、事例の数を多くこなすのではなく、一番効率的でかつ精度の高い答案を作成するための自分自身の手順を確立することを指します。
この手順を確固たるものにするには、勉強量が必要になってくるのはお分かりいただけるのではないでしょうか。
中小企業診断士二次試験で絶対に間違ってはダメなこと
筆者体験談
中小企業診断士二次試験初受験の評価結果は、B・A・A・Cの総合Bでした。二次試験の勉強開始が一次試験合格後だったので、ただ単に勉強が足りなかっただけで、もっと事例をこなせば来年には合格できるだろうと考えて、予備校の通信を利用し一年間勉強しました。数多くの事例を解いたのに結果はB・B・B・Bの総合Bと一年前と比較して、お世辞にも実力が高まったとは言える状況ではないことに愕然としたのを覚えています。
振り返ると、事例を解く手順や解答プロセスのブラックボックス化をホワイトボックス化することを全く考えていませんでした。これを考えることこそが、中小企業診断士二次試験に求められいてる能力であるとともに、問題解決プロセスそのものです。
しかし、目をそむけて、楽なほうである事例の数をこなすことが第一目標となってしまった結果、事例との相性がたまたま良いときしか合格ができない実力しか身につかなかったと感じています。
結論
このように事例を数多くとけば実力が付くという考えは大きな間違いであり、ひたすら様々な事例にあたることはあまり意味のない、とても非効率な勉強方法となりますので注意が必要です。
中小企業診断士二次試験のおススメ勉強スケジュール
中小企業診断士二次試験の勉強は、自分自身で目的をもって進めていかなければ、先ほどの筆者体験談のようなムダな経験をしてしまうことにつながりません。
中小企業診断士二次試験を6回も受けるハメになってしまった経験から、以下をベースにスケジュールを組み立てていくことが効率的な勉強となるはずです。
中小企業診断士試験の本質
中小企業診断士試験の本質を知ることが何よりも重要です。本質を理解していなければ、いつまでたっても博打となってしまいます。いかに自分自身のなかで腹落ちさせられるまで、中小企業診断士に求められる本質を徹底的に考え抜きましょう。
中小企業診断士二次試験の書く力
80分という短い時間のなかで、綺麗な日本語で書ききるのは非常に困難ですし、出題者も求めていません。そんな筆者は、合格する前年度まで綺麗な日本語を書くことに力を注いでいました。それが間違いだと気づくまでにかなりの時間を要してしまいました・・・。
中小企業診断士二次試験の読む力
中小企業診断士二次試験の読む力に、難しいことが求められているわけではありません。中学生までに習う国語の基礎、それと中小企業診断士試験で求められている本質を理解した上での与件の読み方です。
国語力
設問
与件
中小企業診断士二次試験の過去問分析
中小企業診断士二次試験に必要なことを学んだら、あとはひたすら過去問の分析に時間を費やすことをおススメします。予備校の問題はあくまで予備校の問題であって、本試験とは似て非なるものです。過去問を分析すると、とても精巧に与件や設問が作られていることが段々とわかってきます。この感覚がつかめてくると、実力がメキメキとついてきていると言って間違いありません。
組織・人事
設問
与件
解答
マーケティング
設問
与件
解答
生産管理
設問
与件
解答
財務・会計
CVP分析
設備投資の経済性計算
中小企業診断士の二次試験におけるおすすめテキスト〔ふぞろいな合格答案〕の使い方
中小企業診断士の二次試験を勉強していくにあたって、ふぞろいな合格答案を活用した過去問の分析が最強におすすめです。実際、筆者もふぞろいな合格答案を徹底活用しながら過去問の分析を行っていました。
ふぞろいな合格答案の一般的な使われ方だけでなく、筆者独自に編み出した合格に直結する使い方をご紹介しています。
中小企業診断士の二次試験財務・会計におすすめのテキスト4選
中小企業診断士2次試験の合格確立を高めるために、財務・会計の計算力を向上させることは誰もが疑い余地のない見解です。
筆者は、実際にご紹介したテキストを利用して、合格年は76点を獲得できました。
利用した中で、とても有効だったテキストを厳選してご紹介しています。


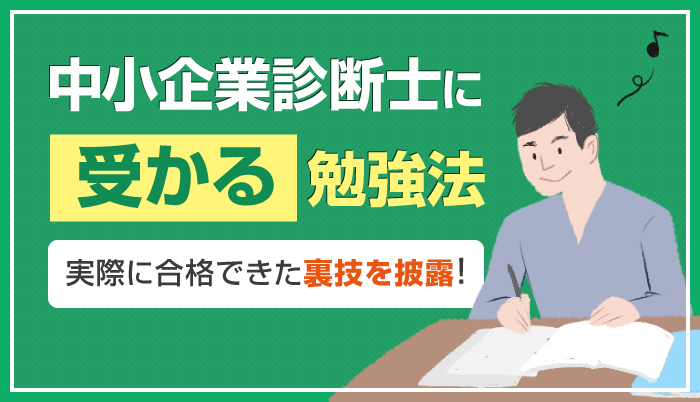












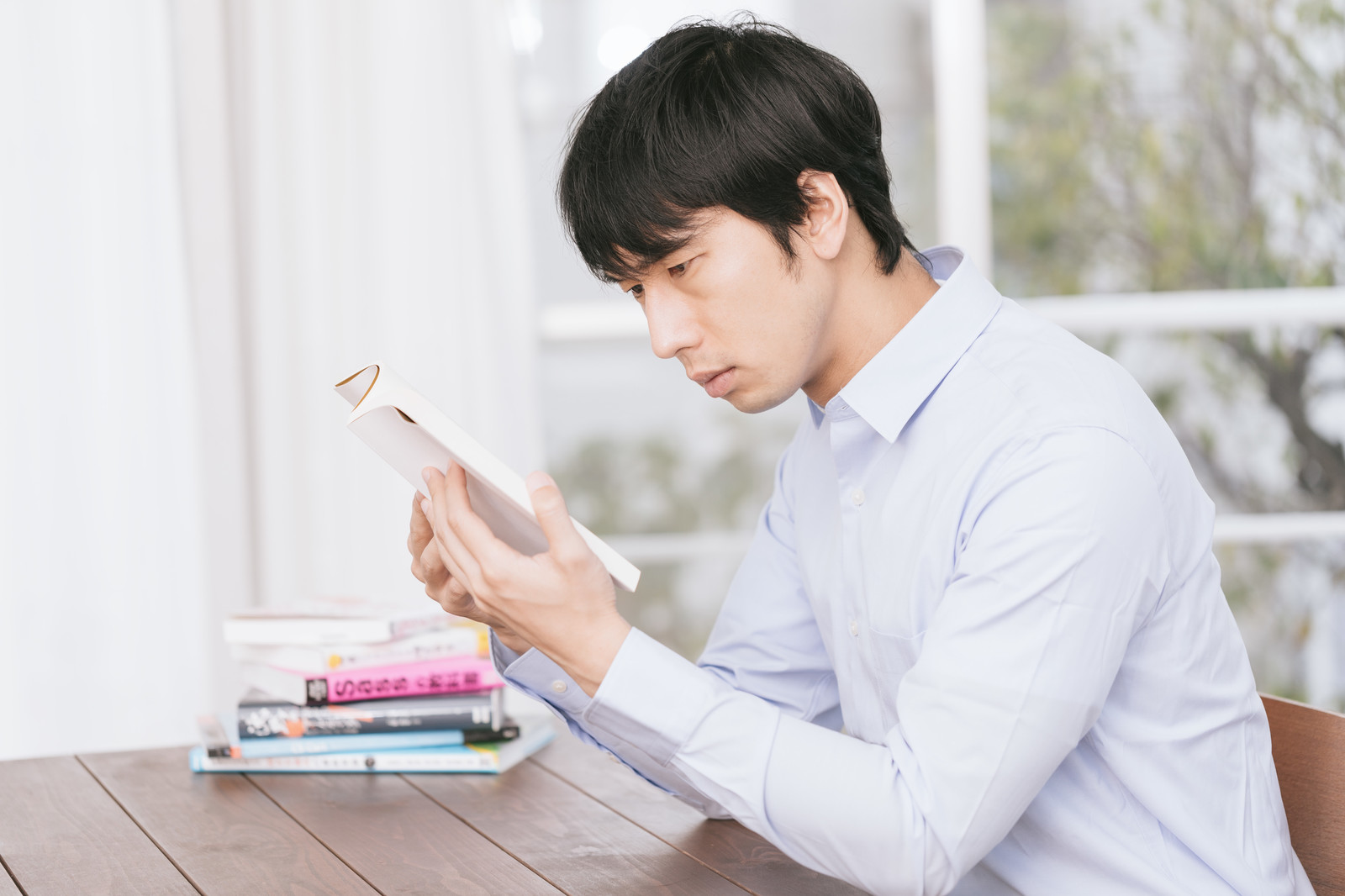



















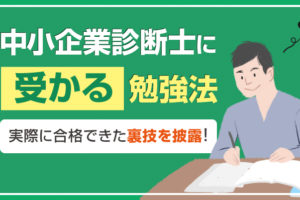




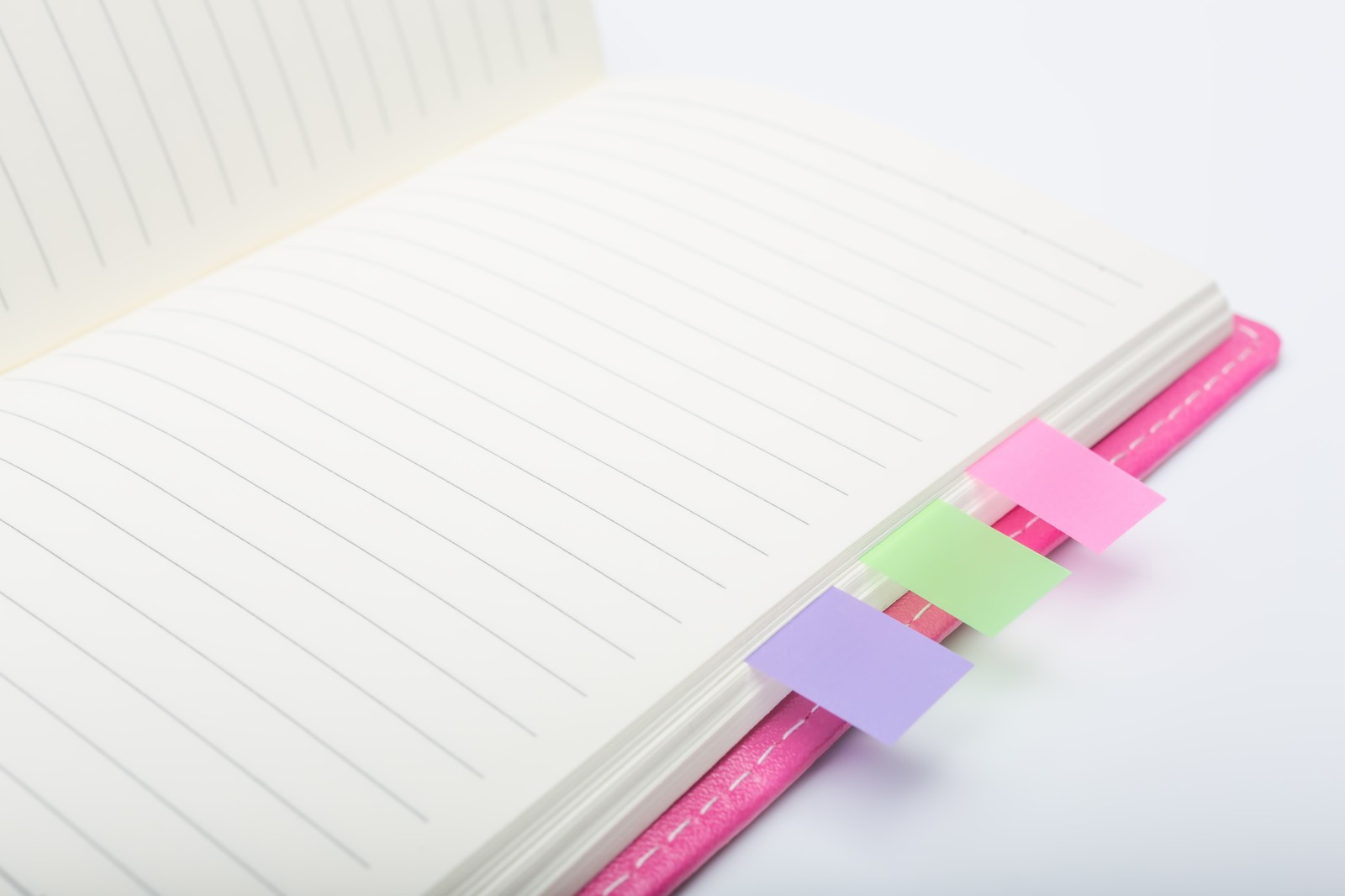



同じような境遇の方により多くお伝えするためシェア いただけると嬉しいです!