中小企業診断士の試験合格率は約4%と、一般的に非常に難易度の高い試験であるため、ただ闇雲に勉強をし始めても、徒労に終わってしまう可能性が高いです。
中小企業診断士の一次試験に4回(全て合格)、二次試験6回受験した末に合格するという、遠回りをした筆者だからお伝えできる独学合格の最短ルートに必要なノウハウ、考え方における情報を詰め込みました。
本サイトを参考にしていただくことによって、一人でも多くの方が独学で中小企業診断士の試験に合格されることを願っております。
中小企業診断士とは【企業の成長】を後押しできる人
筆者が中小企業診断士の試験になかなか合格できなかった一番の要因は中小企業診断士とは国からどんな使命を託されているのかを本当の意味で全く理解していなかったことです。
中小企業診断士の試験勉強を始める前の方だけでなく、受験経験者の皆様もぜひ一読していただき、中小企業診断士が求められている役割を今一度再確認することが、試験合格の道を切り開くポイントとなります。

独学での合格は無理!?合格率、勉強時間など中小企業診断士の難易度をまずは理解

中小企業診断士は一次試験と二次試験に大きく分かれます。また、各年度によってバラツキはあるものの合格率は例年約4%です。
難関資格と位置付けられる中小企業診断士の試験の合格を目指すのであれば、まずは試験制度をしっかりと理解しましょう。

1次4回、2次6回受験の末にようやく合格に至った筆者だからこそ、お伝えできる数字に表れない中小企業診断士の本当の難易度も掲載しています。
中小企業診断士に大学生や主婦でも独学合格できるのか?
大学生や主婦でも中小企業診断士に独学で合格することは不可能ではありません。特に社会人経験のある主婦であれば独学での合格は大いに可能です。
しかし、大学生に関しては独学合格は圧倒的にハードルが高いと言えます。
なぜ大学生にとって中小企業診断士の独学合格は難易度が高いのかについて徹底解説しています。

大学生が中小企業診断士を取得すると就活に有利な理由とあわせて独学での合格難易度について、解説しています。
中小企業診断士に独学で最短合格(半年)するための【60点】勉強法

中小企業診断士試験に最適な勉強法の考え方を勉強開始前に知ることが、最短合格を目指す独学者には最も大切です。
その理由は、中小企業診断士1次試験は7科目と多岐にわたるため、教科書を隅から隅まで覚えることはナンセンスであり、多くの時間を割けない社会人の勉強法としては非効率の極みです。
それでは、中小企業診断士の試験に合格するために必要なこととは何か?そのヒントと裏技を詰めこんであります。

筆者自身もご紹介している方法をとったことで、受験した1次試験は全て合格できています。
独学合格するのにどんな順番で勉強するのがベスト?中小企業診断士の効率の良い勉強スケジュールを解説

中小企業診断士試験を独学で制すには、闇雲に勉強を行うのではなく効率的な勉強スケジュールを立案すべきです。そのためにまずは各科目の特性を知ることが必要となります。
そこでまずは、中小企業診断士の資格取得の第一関門となる一次試験について、各科目の設置目的、出題範囲を把握しましょう。
上記でご確認いただいた通り、中小企業診断士の一次試験は科目が7つもあり、覚えるボリュームが膨大です。

そのため、勉強を開始する前にしっかりとした計画や戦略にもとづいた勉強スケジュールを築くことが、その他受験生と差をつける大きなポイントとなるのです。
中小企業診断士の独学勉強に必須な過去問マスターに重要な【5つ】のステップ

中小企業診断士の試験だけでなく国家資格全てにあてはまることでもありますが、過去問こそが最高の教科書です。
なぜなら、中小企業診断士の試験を運営している中小企業診断協会から出された資格取得に対する唯一にして最大の手掛かりだからです。
専門学校や市販されている教科書をベースにしがちですが、それでは試験合格には遠回りであり、過去問が最高のテキストなのに使い方を勘違いし、一次試験で不合格者が多発します。
そこで、間違った過去問の使い方から脱却し最短ルートでの合格法伝授します。
そして、過去問中心の勉強をし始めると、過去問を解いたが全然歯が立たない、そもそも使い方がわからないといった問題に直面します。
ポイントは、過去問の勉強には
- 論点別で過去問を解く
- 答え合わせ
- 選択肢ごとに振り返り
- 分からなければ教科書に戻る
- キーワード別に分析
の5ステップが存在することです。この具体的勉強方法について解説しています。
独学に使える中小企業診断士のテキスト(教科書)は【5冊】

中小企業診断士は科目数が多いため、分かりやすい教科書でないと理解が進まず、合格が遠のいてしまいます。
教科書に求めるべきは
- 具体例や図解を使いながら平易な言葉で説明しているか
- 過去問をベースに頻出する主要論点に重きをおいた教材構成となっているか
- 過去問の解説がしっかりとなされているか
の3点です。
あとは、上記を焦点にしてとるべき勉強スタイルとして、
- 市販教材のみで勉強する
- 通信講座を利用して勉強する
のどちらが自分にあっているかで選択しましょう。
市販教材のみで勉強する場合は、疑問点を質問できる相手がいないので、自分自身で全て解決するための理解力が求められます。
そのため、理解するまでに時間がかかってしまい、受験勉強が長期化することの方がかえってデメリットになることが多いので注意が必要です。とは言え、教材費としては安くすむので魅力的なのも事実です。

そこで、筆者が利用してきたテキストのなかで優秀だったと感じたテキストをご紹介しています。
※ベースは、TACさんのスピードテキストの利用で問題ありません。
中小企業診断士の通信講座を利用したい方向けに主要5社を徹底比較
通信講座を利用しながら独学で勉強する最大のメリットは、動画で講義が見られるため内容を理解しやすい点です。
反面、市販教材だけでの対応よりもお金がかかってしまうデメリットが存在します。
筆者の同期である中小企業診断士や筆者自身が実際に会社から取り寄せて利用してみた結果から、コスパが高い通信講座だけを厳選して5社紹介しています。
中小企業診断士一次試験の突破に効果的な独学勉強テクニック

中小企業診断士の一次試験では、全く見たこともない問題に必ず直面します。この見たこともない問題に対応するために、専門書で勉強しようとしてしまいがちですが、中小企業診断士試験ではそこまで細かい知識は求められていません。
なぜなら、全く知らない問題でも、国語表現への着目で正答を導くことが可能な場合があるからです。
むしろ、そのような場合こそ国語表現への着目で正答にたどり着ける可能性が高いとも言えます。そんな、知識ゼロでも正答するために必要なたった3つのコツをご紹介します。
中小企業診断士の1次試験科目の運営管理や経営情報システムには3文字英語(MPS等)多く登場します。同じような3文字単語が多く頭の中でこんがらがってしまったり、覚えても覚えても頭に入らないといった状況にでくわします。
この状況を解決するコツは意外と簡単で、言葉を見て頭の中に映像がでるかどうかです。
言葉を見ただけで映像が出るはずがないと思われるかもしれませんが、そのためのコツは意外と簡単なのです。
中小企業診断士二次試験の独学合格を見据えた【超効率的】な勉強法

中小企業診断士の一次試験勉強を続けながら、二次試験も同時並行で行うことは、時間的制約からとても大変です。そこで、一次試験の勉強を中心に据えながらも、最小の労力で二次試験の勉強も同時並行するための具体的ノウハウをご紹介しています。
中小企業診断士の2次試験では、能動的に行動できる人が求められています。
能動的とは、
- 現場感覚
- 戦略的
- 助言
の3つに言い換えられるのです。
これを測るために二次試験では、一次試験の知識は丸覚え対応ではなく、覚えた内容を事例企業にあてはめて、カスタマイズできるかどうかが合格の大きなポイントとなります。
中小企業診断士の二次試験を見据えた一次試験学習が重要ですが、並行勉強が困難なのも事実として存在します。
この問題を解消するために効率的な勉強方法は、一次試験の過去問で二次試験の知識整理をしてしまうことです。
筆者が実際にとりいれていた時短勉強法についてご紹介しています。
【合格後の世界】中小企業診断士として【年収3千万以上稼ぐ】も不可能じゃない
中小企業診断士の取得目的に独立を視野にいれていて勉強している人も多いのではないでしょうか?
そこで、語られることが少ない独立後の年収について、独立1年目の診断士にリアルガチな情報を根掘り葉掘りインタビューしました。


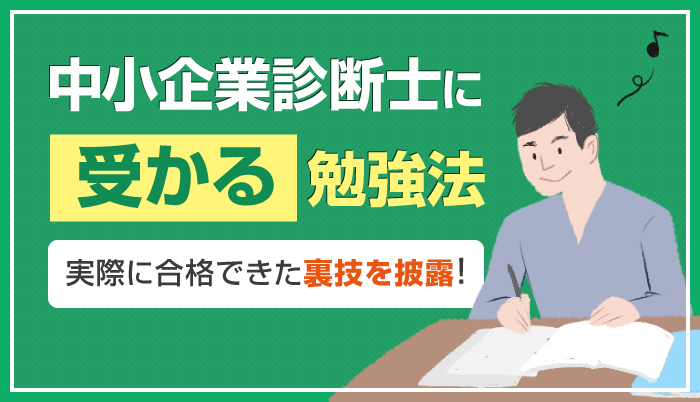




実際、筆者は中小企業診断士とは何者なのかについて腹落ちできたことが二次試験の突破する転機となりました。