- 中小企業診断士の一次試験と並行しながらも二次試験の勉強をちょっとでもいいから進めたい方
- 中小企業診断士の二次試験の問題を見て、一次試験との違いに愕然とした方
- 中小企業診断士の二次試験の存在が気になりつつも、一次試験勉強に手いっぱいで、二次試験の全貌をまだ知らない方
- 中小企業診断士の二次試験は能動的な行動ができる人を求めている
- 能動的な人とは、現場感覚、戦略的、助言の3つに集約される
- これを体現するには、中小企業診断士の一次試験の知識は丸覚え対応ではなく、覚えた内容を事例企業にあてはめて、カスタマイズできるかどうか
- 中小企業診断士の一次試験勉強と並行で二次試験勉強を行うなら、事例4(財務・会計)の短い与件文を使った経営課題の特定練習がおすすめ
ツイッターで、疑問や質問、リクエストを随時お受付しています。
中小企業診断士試験で知りたい内容あれば、リクエストください!
どこまで実現できるかわかりませんが、鋭意努力して記事化していきます!#中小企業診断士試験 #中小企業診断士 #二次試験 #一次試験も要望があれば #リクエスト情報絶賛募集中— aerozol (@_aerozol) 2017年12月20日
さらに、匿名で質問ができる「質問箱(こちらをクリック)」にも最近登録しましたので、ツイッターアカウントを知られるのが恥ずかしいわという方は、質問箱(こちらをクリック)からご質問ください!
ちなみに、ツイッターのメッセージに送っていただいても構いません。
すみません、以上宣伝でした。
ありがたいことに、ツイッターでリクエストをいただきました。
関係ない部分もあるかもしれませんが、その時のやりとりは以下の通りです。
ご返信ありがとうございます😊!考えてみます!
ちなみに解き方の手順なのか、一次試験の知識を二次試験でどのように使うかなど、どの辺りが知りたいとかありますか?— aerozol (@_aerozol) 2018年2月17日
ご返信ありがとうございます!
いただいた内容で記事作ってみます!副教材としてなら、参考書ご紹介できるものあります。メインとしてだと、ふぞろい以外ないなと思っていました☺️!近々アップできるよう頑張ります!— aerozol (@_aerozol) 2018年2月17日
てる@診断士受験生さんは、予備校に通われていると思われますが、独学者の方であっても、同様の悩みをお持ちの方は多いのではと容易に想像できます。
筆者自身の二次試験に対する経験と重ね合わせると、こんな悩みをお持ちなのではないかとの仮説を立てました。
- 二次試験の科目別の特徴がよくわからない
- 二次試験で使う知識ってどんな内容なの
- 一次試験で覚えた知識を二次試験でどのように使えばよいか知りたい
- 一次試験の勉強だけでも大変なのに、並行して二次試験の勉強も本当にできるの
このような、悩みへのヒントとなれるような内容を綴っていきます。
中小企業診断士の二次試験とはどんな試験
まずは、中小企業診断士の二次試験について調べみると、中小企業診断協会のホームページには以下のように記されていました。
中小企業診断士となるのに必要な応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、診断及び助言に関する実務の事例並びに助言に関する能力について、筆記試験及び口述試験を行います。
中小企業診断士の二次試験では応用能力を試すことが目的となっています。つまり、応用能力をみにつけることができれば、中小企業診断士の二次試験に合格できるといえます。
しかし、応用能力という言葉は抽象的であり、何を指しているのか分かりません。
中小企業診断士の一次試験と二次試験の違い
この応用能力とは何か、1次試験との違いを出題形式などから考えてみます。
結論からお伝えすると、
応用能力とは、能動的に行動できる人かどうか
であると筆者は考えています。
| 項目 | 1次試験 | 2次試験 |
|---|---|---|
| 目的 | 中小企業診断士となるのに必要な学識を有するか | 中小企業診断士となるのに必要な応用能力を有するか |
| 形式 | マークシート | 記述 |
| 求められる能力 | 与えられた選択肢から正答を導く | 与えられた情報を自身で処理し、解答をイチから作成する |
| 解答 | 公表 | 非公表 |
| 違い | 受動的 | 能動的 |
出題形式
まず、マークシートか記述の違いについてです。
- マークシート
- 記述
- 一次試験
- 二次試験
- 一次試験が教習所内での講義
- 二次試験が教習所内での実技
- 実務補習が一般道路での仮免
- 現場感覚
- 戦略的
- 助言
- 現場感覚
- 戦略的
- 助言
- 現場感覚:現状を的確に把握
- 国語力
- 設問編
- 戦略的:あるべき姿とシナリオを描く
- 与件編
- 助言:自発的行動を促しつつアドバイス
- 権限が少なく、責任が多い方のモチベーションが低下
- 意思決定が遅くなる
- 権限を持つもの想いなどが尊重されるため、最適解ではない意思決定が働く可能性がある
- 第6段落
- 第8段落
- 第4段落
- 第8段落:販売管理費
- 第4段落:売上原価
- 権限が少なく、責任が多い方のモチベーションが低下
- 意思決定が遅くなる
- 権限を持つもの想いなどが尊重されるため、最適解ではない意思決定が働く可能性がある
- 一次試験を現在勉強中で、二次試験も見据えた効率的な勉強方法を模索している方。
- 入門者向けの書籍ではないため、余力がある方のみおすすめします。
- 中小企業診断士を志すもの全ての方必読です。
- 生産現場に携わったことがなく教科書や過去問題をみてもイメージがわかない方
- 中小企業診断士の二次試験事例3の問題を見て、注目すべき点がわかなかった方
- 中小企業診断士の二次試験は能動的な行動ができる人を求めている
- 能動的な人とは、現場感覚、戦略的、助言の3つに集約される
- これを体現するには、中小企業診断士の一次試験の知識は丸覚え対応ではなく、覚えた内容を事例企業にあてはめて、カスタマイズできるかどうか
- 中小企業診断士の一次試験勉強と並行で二次試験勉強を行うなら、事例4(財務・会計)の短い与件文を使った経営課題の特定練習がおすすめ
選択肢が与えられているため、正答かどうかを判断できるかの正確性が問われます。
一方で記述の場合は、選択肢がも与えられていない場合だと、自分自身で情報の取捨選択をしながら解答を組み立てなければいけません。
模範解答の有無
一次試験は当たり前ですが、解答が公表されます。
これは中小企業診断協会側が、進むべき方向性を提示してくれているとも言えます
二次試験は解答が発表されません。
先ほどの逆で、中小企業診断診断協会側は、進むべき方向性を提示してくれていません。
この事実から言えることは、自分自身で考える力をもって欲しいというメッセージを伝えようとしているのではともとれます。
これらをまとめると、一次試験で受動的な能力を、そして二次試験で能動的な能力を高めようしていると考えられます。
自動車の免許取得をしようとした場合に例えると、
となります。
能動的をもっと掘り下げてみると
応用能力とは、能動的な行動ができる人とお伝えしました。
何となくご理解いただけたと思いますが、まだ抽象的な部分があるので、もっと掘り下げていきます。
中小企業診断士に求められる基本能力
中小企業診断士の二次試験を免除する方法として、中小企業診断士の素養を学ぶ養成課程に入学するルートがあります。
ただし、誰でも入学できるわけではなく、中小企業診断士としての資質を持っているかが入試で問われます。
この養成課程がカリキュラムを組む際に求められる内容が存在するのですが、ここに中小企業診断士の能動的な行動(応用能力)ができるかどうかの内容が記載されていましたので、ご紹介します。
中小企業診断士の二次試験で求められる素養も同じだと捉えてください。
養成する中小企業診断士像
全社的視点で、中小企業経営についての現場感覚に根ざした戦略的な問題発見・問題解決について、的確な支援施策の活用を考慮に入れた助言ができる経営コンサルタントを養成する
企業の現状を的確に把握するとともに、中小企業の特性を踏まえて企業経営を考えることができる能力。
5~10 年後の競争優位を築けるあるべき姿とシナリオを描くことができる能力。
経営目標の達成に向けて、経営者・社員の自発的行動を促しつつアドイスができる能力。
参考:中小企業庁:登録養成課程を実施するためのカリキュラム等の標準モデル
これは二次試験に一番求められていることとして、かねてから筆者がお伝えしている、(1)経営課題をしっかりと把握できる、(2)それを解決するためのストーリーを描けるか、と同じ内容です。
先ほどご紹介した二次試験の目的が記載されいている文のなかの助言に注目してください。
中小企業診断士となるのに必要な応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、診断及び助言に関する実務の事例並びに助言に関する能力について、筆記試験及び口述試験を行います。
なんと助言が、この短文の中で2回も出てきているのです。これは、たまたまではなく意図してのことだと考えます。
中小企業診断士の歴史でお伝えしましたが、昔は診断のみにスポットがあたっていましたが、経済環境が複雑化する近年おいては、診断はもちろんのこと、助言にスポットがあたっている歴史的な変遷と関係があると言えそうです。
助言とは、自発的な行動を促しつつアドバイスすることです。
つまり、明日にでもすぐに行動が起こせるほどに咀嚼したより具体的な提案を中小企業診断士の二次試験のなかでも行っていくことが、得点につながることを示唆しています。
重要ですので、能動的な行動ができる人(応用能力として求められいる)の要素を記載します。
中小企業診断士の二次試験に合格するには、本番で以下を表現するトレーニングが必要となります。
全社的な視点での問題発見・問題解決できる提案力
その要素として、
現状を的確に把握
あるべき姿とシナリオを描く
自発的行動を促しつつアドバイス
中小企業診断士の二次試験の特徴
中小企業診断士の二次試験で応用能力が試されているのか、そしてその応用能力とは何かも分かったら、その次は二次試験の特徴を抑えていきましょう。
全科目共通
試験スケジュール
| 科目 | 試験時間 | 配点 |
|---|---|---|
| 事例1(組織・人事) | 9:50~11:10(80分) | 100点 |
| 事例2(マーケティング) | 11:40~13:00(80分) | 100点 |
| 事例3(生産・技術) | 14:00~15:20(80分) | 100点 |
| 事例4(財務・会計) | 15:50~17:10(80分) | 100点 |
全科目共通で必要なスキル
全科目共通で必要なスキルとしては、読む力・考える力・書く力の大きく3つとなります。
この中で最重要(90%程度の割合を占めると筆者は思っています)なのは、読む力です。
また、読む力と考える力はニアリーコールです。読む力さえしっかりしていれば、考える力は自然と身についていきます。
先ほどの現場感覚、戦略的、助言の3つの言葉がどのように当てはまるのか見ていきましょう
二次試験に当てはめてみると、与件文と設問文から出題者の意図をしっかりと見抜けるかです。そのためには、文章や段落を構造化して大枠で把握できるかと、与件や設問を一次試験で習った知識に置き換えながら考えることができるか、が必要です。
二次試験攻略のためには、国語の基礎力が求められます。といっても小中学生の時に学んだ本当に基本的な部分さえ抑えられれば問題ありませんので、ご安心ください。
出題者は、事例企業を成長・発展に導くためのストーリーを必ず描いています。その部分解が各設問にあらわされており、すべてをつなぎ合わせると、ストーリーが完成するようになっています。
あるべき姿とシナリオを描くためには、経営課題の特定把握ができなくてははじまりません。
具体的に、どのように経営課題を把握するのかについて、ご説明しています。
自発的な行動を促しつつアドバイスとは、明日にでもすぐに実行できるようなより具体的な内容が求められます。
それは、
与件や設問で使われているワードの活用一次試験で学んだ知識の活用
です。
二次試験で一次試験の知識をどのように使う必要があるのかを先に知ったうえで、一次試験勉強を行うことが、時間対効果の高い勉強法となります。
詳細は、後述の「過去問を見てみよう」にてお伝えします。
事例1(組織・人事)の特徴
事例1(組織・人事)の試験特徴は、設問文の問いかけがとても抽象的で、出題者が意図している内容を掴みにくいことが挙げられます。これは、組織・人事は無形であることに由来していると筆者は考えています。
あくまで、事例1は組織・人事の内容がとわれていることを忘れてはいけません。
事例2(マーケティング・流通)の特徴
事例2(マーケティング・流通)の試験特徴は、小売・サービス業の事例企業が登場することが多い傾向にあります。
日々の生活と密接に関連しているがために、自分が体験した事柄を記載してしまいがちです。
自分自身の経験が豊富なゆえに、試験後の感触と評価が反比例する、乖離が起こりやすい事例と言えます。
あくまで、中小企業診断士の二次試験ですので、出題者が期待する内容を推測して、解答をかいていくことが重要です。
事例3(生産・技術)の特徴
事例3(生産・技術)の試験特徴は、生産現場で発生している問題をしっかりと把握し、その問題点を解決する改善策を提示していくことです。
一見、生産現場に関する内容であるため、難しそうだなという感じるかもしれませんが、問題ありません。
生産現場に関する事柄を取り扱っているだけで、問題構成としては、4事例のなかでシンプルかつ国語の問題に一番近いと言えます。
事例4(財務・会計)の特徴
事例4(財務・会計)の試験特徴は、当たり前ですが計算問題が含まれていることです。しかし、企業の経営課題を解決する提案を論述できなければ、計算問題が全てとれてもA判定がとれません。
財務・会計であっても、経営課題を解決するためのストーリーを描くことが何よりも重要です。
過去問を見てみよう
中小企業診断士の一次試験と同様に、実際の過去問を見て、どのように問われるかを理解することが第1歩となります。平成20年度の事例1(組織・人事)第5問を使ってご説明したいと思います。
設問文
収益改善に取り組む現社長は、工場長を取締役に昇進させて権限強化を図った。それまで料理長が掌握していた権限を工場長に移管したことが、コスト削減にどのような効果を及ぼしたと考えられるか。それが及ぼす効果について、150字以内で述べよ。
工場長を取締役に昇進させて権限強化を図ったとなっています。
この文脈から読み取るに、権限責任が一致していなかったことが原因でコスト削減が働いていなかったと考えられます。
まずは、権限責任不一致の時におこる現象を思い出しましょう。
中小企業診断士の一次試験で習った知識に該当するのは、組織の5原則のなかの「権限責任一致の原則」です。
ヒントは、権限責任一致の原則で覚えた内容の裏返しが答えです。
これを念頭に、該当する与件段落をピックアップします。
与件文
同年、2代目社長の叔父の後を受けて、40歳代前半の、創業者の長男で専務取締役であった現社長が事業を引き継ぎ、「安心して召し上がっていただける商品をリーズナブルな価格で」という創業以来のモットーを継承しながら、新しい体制をスタートさせた。
会社の経営理念が記載されています。権限責任を強化を図った理由は設問文にも記載がありましたが、与件文からもリーズナブルな価格で提供できないことが原因だとわかります。
さらに、客の嗜好や季節に合わせて、メニューの改訂を定期的に行うことを求められるようになった。航空会社のニーズを充足するためには有能な料理長の存在が不可欠であり、A社でも有名なレストランのシェフを長年経験し、料理界でその名をよく知られている人材を料理長として迎えた。
料理界で知られる有名な人材料理長として採用したとのことです。
この文章とコストの関係を考えると、コストを意識しない高級食材などを利用したメニューを提供していたのではとの推測は思い浮かぶのではないでしょうか。
A社が次なる事業拡大に向けて一歩踏み出したのは、創業後15年を経た頃である。A社の主力工場となった第2工場に隣接する土地に大型冷蔵室を備えた工場を増築すると、新たに2社の外国航空会社との取引も開始するようになった。当時の主力製品は、カップ入りジュース、サラダ用カット野菜とカットフルーツであった。かつての主力であったミニカップ入り食品の売上は創業以来ほぼ横ばいで推移し、前者の売上に占める割合は次第に縮小してきた。自宅併設のミニカップ入り食品製造の工場の規模や体制は、現在に至っても創業当時とほとんど変わっていない。
売上に占める割合が縮小しているのに、規模も体制も変えていないのであれば、コストが相対的に上がっていくのは当たり前ですよね。社長は、料理ちょうではできなかった、工場体制の最適化を臨んで、工場長に権限強化を図ったと理解できます。
規模や体制がそのままということは、人件費を含む販売管理費が適正な費用支出になっていないと言えます。
原材料費の抑制となるので、損益計算書でいくところの売上原価となります。
解答
与件と設問から導かれた解答を記載します。
効果は、(1)航空会社のニーズを充足するために必要な客の嗜好や季節に合わせてメニューの改訂を行う際に採算コストを意識した原材料の選定で売上原価の低減を図ること、(2)自宅併設のミニカップ入り食品製造の工場を売上規模に適した規模や体制に再構築の実施により販売管理費の低減を図ること、である。
中小企業診断士の一次試験知識で使われた内容をもう一度、振り返ってみる
先ほど権限責任不一致によるデメリットして、以下の3つを挙げました。
このうち、使用した知識は3つ目でした。
しかし、解答を見ていただけるとわかりますが、知識自体をそのまま活用しているのではなく、最適解ではない意思決定が働いている部分を与件文と設問文から推測して、与件の言葉を利用しながら、解答を組み立てています。
中小企業診断士の二次試験|科目別のおすすめテキスト(補助教材)
全科目共通
ふぞろいな合格答案シリーズ
合格者だけでなく不合格者(評価付き)の生々しい答案が掲載されています。自身の解答に加えて、これらの再現解答を分析することで合格確率が高まります。
中小企業診断士試験問題集2次の知識はこれ1冊
一次試験で学んだ知識をどのように二次試験で活かすのかに焦点をあてた、問題集で、一次試験と二次試験の橋渡しをしてくれるのに非常に優れたテキストです。
筆者が購入した時は誤植がびっくりするほどあり、とてもみずらかったのですが、版数を重ねたことにあわせて誤植も修正なされていますので、ご安心ください。
事例1(組織・人事)
中小企業診断士試験の出題委員でもある「桑田耕太郎」氏の組織論が、おすすめの参考書籍です。
組織論補訂版
少し難しめですが(筆者は書かれている言葉も理解できなかった部分がありました)、組織構造や文化、プロセスなどを研究データを示しながら、分析しているページ中盤以降はとても参考になります。
事例2(マーケティング・流通)
こちらも中小企業診断士試験の出題委員である「岩崎邦彦」氏のスモールビジネス・マーケティングが、おすすめのテキストです。
スモールビジネス・マーケティング
いわずと知れた、中小企業診断士の二次試験マーケティング本です。
本書をもとに、中小企業診断士の二次試験の事例2が作られていると言っても過言ではありません。
その証拠に、信用、こだわり、ブランド、経験、知識、技術、ノウハウ、関係性といったワードは与件文の中で数多く登場しますが、これは、スモールビジネス・マーケティングで最重要項目として挙げられています。
筆者は、岩崎尚人さんのセミナーにミーハーな気持ちで参加したことがあります。今でも印象に残っているのは、スモールビジネスで重要なのは、ブランディングをいかに上手にできるか。そのためには、自社が一番と誇れる観点でマーケティングをしていくことだとおっしゃていました。
これは、中小企業診断士の二次試験の鉄板セオリーである機会(チャンス)に自社の強みである経営資源を投入して、成長発展を目指すことに通じています。
中小企業診断士の二次試験勉強だけにとどまらず仕事でも本書の考え方は適用できるため、買っておいて損はない一冊だと断言します。
事例3(生産・技術)
中小企業診断士の試験と直接の関係はありませんが、生産管理の現場をイメージがわかない人にもってこいのおすすめテキストです。
このテキストは小説なので、とてもとっつきやすいです。
機械メーカーの工場長であるアレックスが、工場閉鎖まで3ヶ月と言われた中で、苦悩しながらも生産現場の業務改善を推進していくといったお話になっています。
おすすめする理由として、生産管理に出てくるTOC(制約条件理論)をベースに話が展開されていきます。
中小企業診断士の二次試験事例3(生産・技術)も、TOC(制約条件理論)をとても意識した与件や設問の作りとなっています。小説を読むことで、どのような点に注目すればよいのかといった勘所が理解できるようになることから、中小企業診断士の二次試験と親和性がとても高いおすすめのテキストです。
小説を読む時間がとれないといった方には、コミック版も出ているので、そちらをおすすめします。
事例4(財務・会計)
事例4(財務・会計)については、こちらでおすすめのテキストをご紹介しています。
中小企業診断士の一次試験の勉強との並行でも二次試験勉強で押さえておきたいこと
いろいろとご紹介をしてきましたが、そうはいってもまずは中小企業診断士の1次試験突破することが最優先です。
その中で一番重要なことは、なんといっても経営課題を精度高く特定できるようになることです。
これは、中小企業診断士の一次試験勉強中の方であっても、事例4で使われる短文の与件を使って練習すれば、休憩時間で頭の体操がてら取り組むことができます。
経営課題の把握ができれば、解答の6割は出来上がったと言っても過言ではありません。
詳細はこちらをご覧ください。


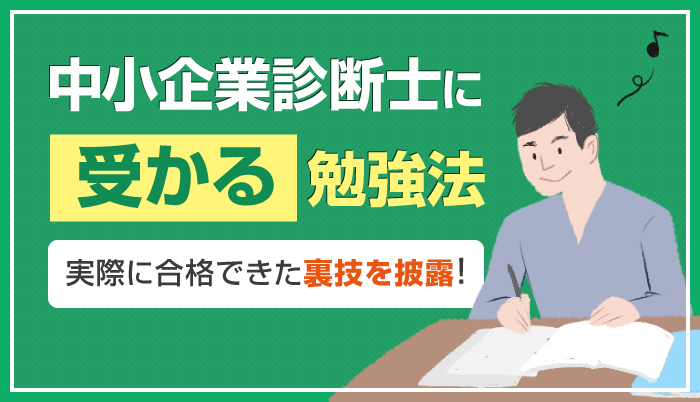





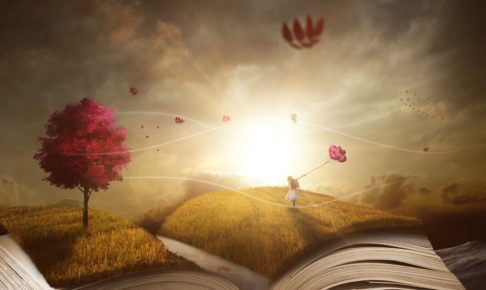



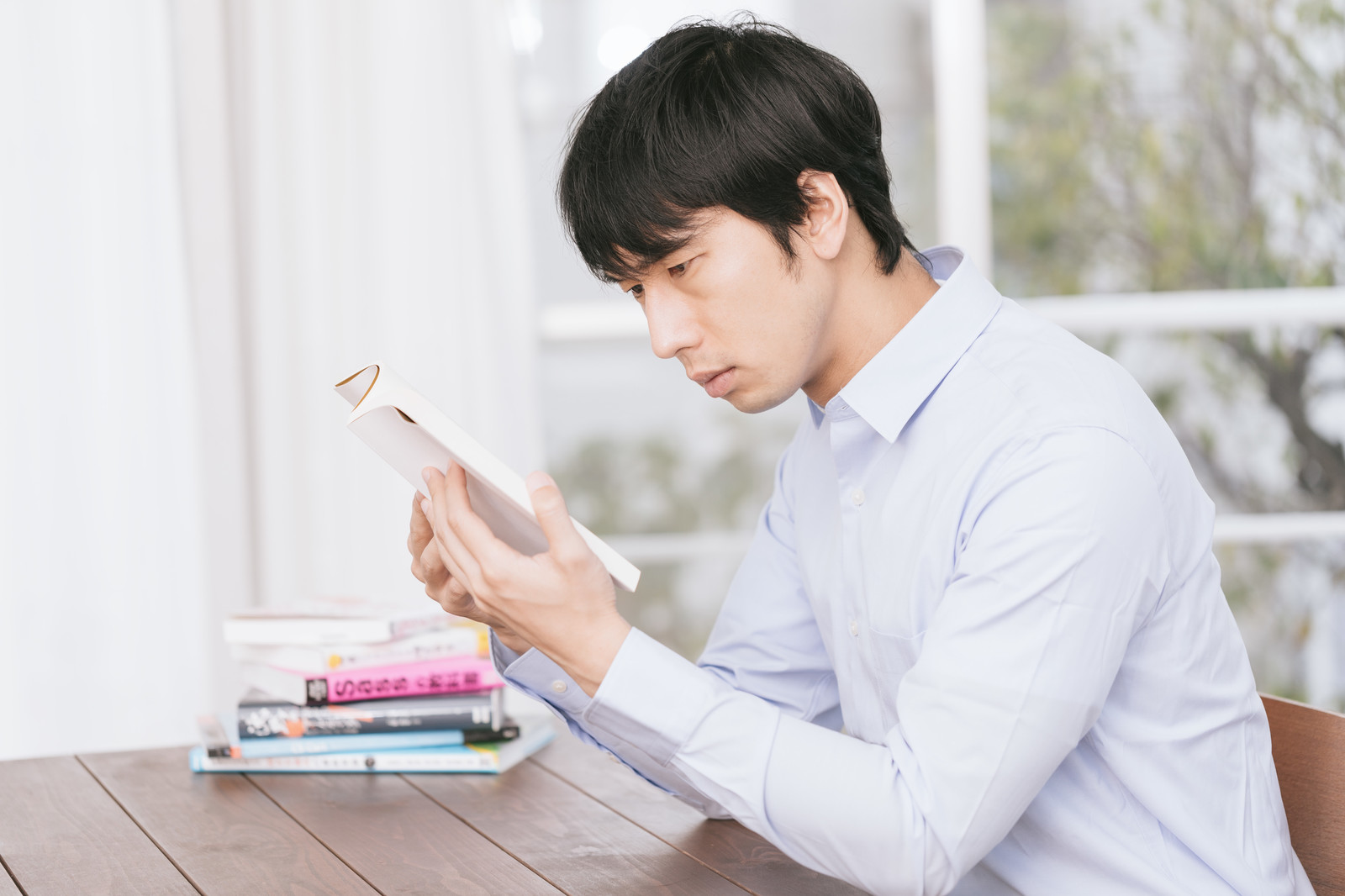


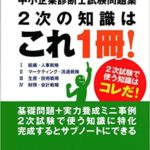









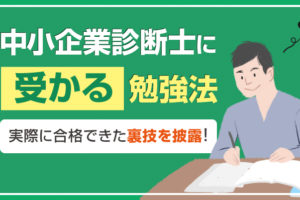





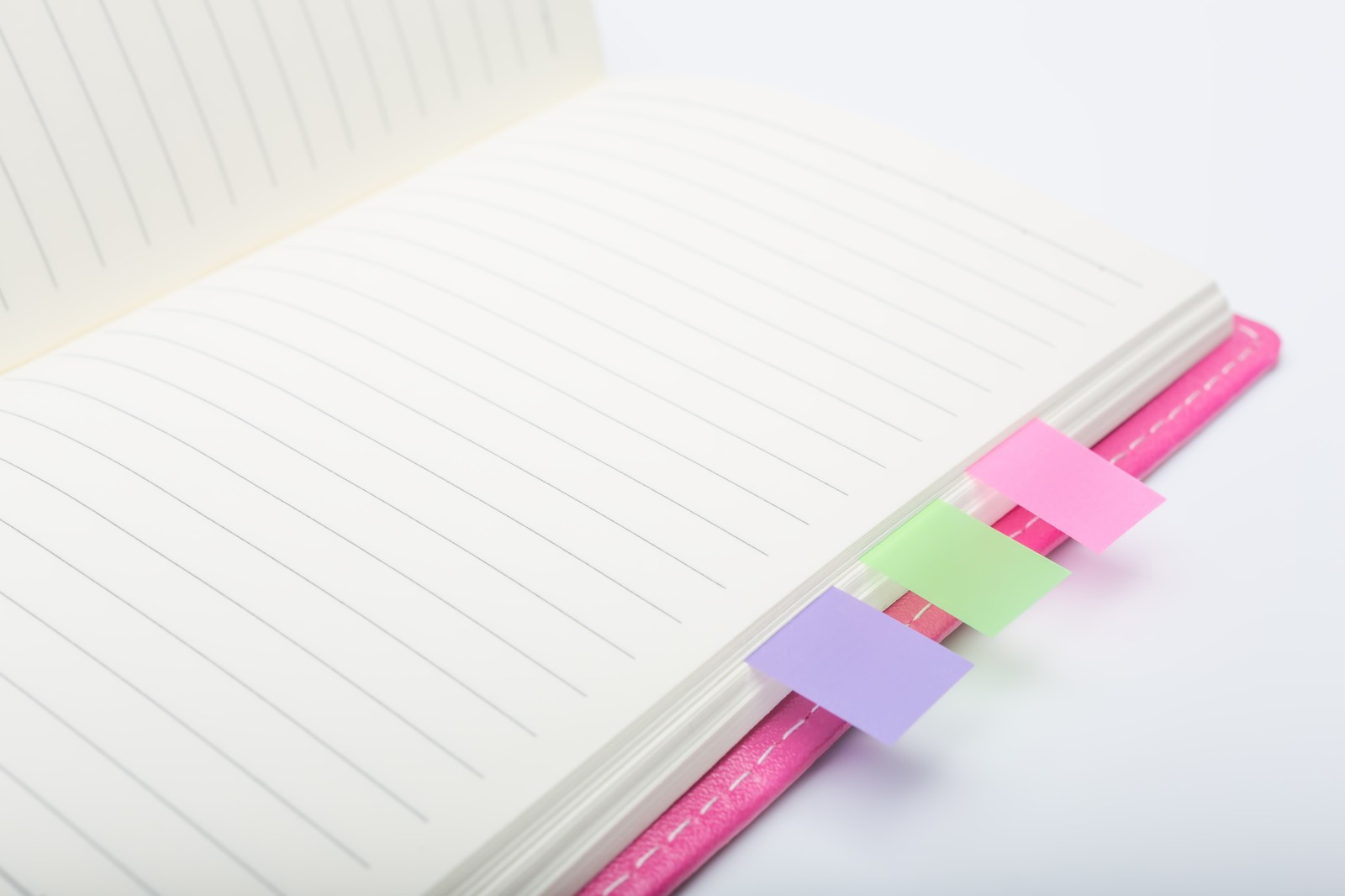


同じような境遇の方により多くお伝えするためシェア いただけると嬉しいです!