

二次試験の合格を見据えた一次試験の勉強法を模索されるなんて、素晴らしい。未来を見据えた行動を模索していることは、とても中小企業診断士向きだと思います。
私が受験生だった時なんて、とりあえず一次試験に合格だけで、二次試験はそのあと考えればよいと思っていました。結果、苦労することになるのですが。。
もちろん、非効率な学習ほどムダな勉強はありません。企業経営理論の一次試験の過去問を使って、二次試験にもつながる勉強法をご紹介していきます。
- 平成20年度第8問設問3を例に解説
- モラールには、内発的動機づけと外発的動機づけにわけられる
- 両者の具体的な内容を過去問を使って整理しておけると、二次試験の特に助言(提案)問題の記述の際にとても使える
中小企業診断士の一次試験科目である企業経営理論
平成20年度第8問(設問3)
企業が設立される理由はさまざまであるが、近年の会社法の施工や証券市場の整備によって創業やIPOが容易になったことも重要な要因である。しかし、制度が整備されたとはいえ、創業した企業を発展させ、持続的成長を図ることは容易ではない。零細企業を脱してIPOが可能な企業への成長を目指す場合、創業してから安定成長の軌道に乗るまでに克服しなければならないいくつかの壁がある。
創業から間もなく直面する壁は、企業として自立するために創業時の制約条件を克服することである。これを克服して従業員が増え、会社としての形態が整ってくると、やがて創業者は創業時の熱気を維持し組織の活力を高めることを課題として自覚するようになる。
文中の下線部の課題は、会社の成長にともなってしばしば発生する課題である。経営者は多くの時間をこの課題の克服のために割いているが、その対応として、最も不適切なものはどれか。
ア会社の目標と計画に沿って個人別の目標を設定する場合、部下の参画を求め、主体的な目標管理を促すとともに、新入社員に対しては上司が積極的に目標設定を指導する。
イ会社への忠誠心を高めるために、個人別に業績を評価し、それを給与や処遇に連動させた計数管理を徹底する。
ウ職務へのコミットメントを高めるために、個人別に権限と責任を明確にした管理システムを導入する。
エ創業の思いを共有するため、トップは従業員との対話の機会を増やし、創業時の思いや成功・失敗談を語るとともに、個々の仕事への意欲的なチャレンジを奨励する。
本設問は、モラールに関する内容について問われています。
二次試験でモラールときたら、人事戦略であり、具体的な切り口は次の通りです。
- モラール
- 能力
これは、とても汎用的な切り口なので覚えておきましょう。
話を戻して、問題をみていきます。
問題の解説
本問題は、最も不適切な内容を選択しろと問われています。
先に答えをお伝えすると、イが正解となります。
これは、イの解答の内容の因果関係や文章が間違っているのではなく、創業時の熱気を維持することを考えたときのモラール策として、適していないからです。
モラールとは、内発的動機づけと外発的動機づけに分けられ、イは後者、それ以外は前者に分けられることがその理由です。
- 内発的動機づけ
- 外発的動機づけ
内発的動機づけ
内発的動機づけとは、個人の内面から発せられるモラールの高まりを指します。内発的動機づけを刺激する行為は、尊重、承認などになります。
この具体的な内容が以下の色付きの部分となります。
二次試験として重要なことは、この具体的な提案項目として何が当てはまるのかを知識的に覚えておくことです。
理由は、二次試験の設問は診断(分析)もしくは助言(提案)の設問で全て成り立っており、その中で助言(提案)の際の引き出しとして活用できるからです。
- 選択肢:ア
- 選択肢:ウ
- 選択肢:エ
会社の目標と計画に沿って個人別の目標を設定する場合、部下の参画を求め、主体的な目標管理を促すとともに、新入社員に対しては上司が積極的に目標設定を指導する。
職務へのコミットメントを高めるために、個人別に権限と責任を明確にした管理システムを導入する。
創業の思いを共有するため、トップは従業員との対話の機会を増やし、創業時の思いや成功、失敗談を語るとともに、個々の仕事への意欲的なチャレンジを奨励する。
一次試験の過去問を解いた際にこれらの内容をついでにまとめておくと、二次試験の問題を解く際に非常に強力な武器として役立つこと間違いなしです。
- 部下への参画をはかる
- 主体的な目標管理を促す
- 権限と責任の明確化
- 従業員との対話の機会を増やす
- 意欲的なチャレンジを奨励
外内発的動機づけ
外発的動機づけとは、外側から評価や賞罰、規則などの人為的に、モチベーションを高めることを指します。外側からの要因となるため、モチベーションの効果と手しては長く続きません。
具体的な内容が選択肢イとなります。
-
選択肢:イ
個人別に業績を評価し、それを給与や処遇に連動させた計数管理を徹底する。
内発的動機づけは、それなりに知識の引き出しとしてまとめられましたが、外発的動機づけは、問題の構成上1つしか本問題からは覚えられません。
さらに知識の深堀をしていくには、類似の過去問題を解いた際に外発的動機づけの問題を整理する、もしくは、スピードテキスト等のテキストで振り返りって整理するといった方法が考えられます。
例えばそれ以外に付け足すとしたら、
- 給与や処遇に連動させた計数管理の徹底
- 時短制度の導入
- 育休制度の導入
- 評価制度項目の明確化
- 人事考課制度の明確化
などですね。この辺りを、類似過去問などで何がとり上げられているのか探ってみてください。
学んだ知識がどのように二次試験で活かされるのかチェック
最後に、例として挙げた内発的動機づけや外発的動機づけで覚えた内容がどのように活用されるのかを見ていきます。
平成26年度の二次試験組織・人事事例の第5問解答をご紹介します。
もっと詳細を知りたい方はこちらをご覧ください。
A社は、若干名の博士号取得者や博士号取得見込者を採用している。採用した高度な専門知識をもつ人材を長期的に勤務させていくためには、どのような管理施策をとるべきか。中小企業診断士として100字以内で助言せよ。
との設問に対して、筆者の解答は以下の通りです。
解答
とるべき施策は(1)従業員のキャリアプランを考慮した長期的な教育計画を策定し能力の向上を図ること、(2)新製品や技術開発に関する提案制度や表彰制度、人事考課制度を導入しモラールの向上を図ること、である。
注目してほしいのは、色がついている部分です。
提案制度や表彰制度については、表現こそ違いますが。内発的動機づけでまとめたなかの、意欲的なチャレンジを奨励に関するに該当します。
さらに、外発的動機づけとして人事考課制度の導入を利用しています。
モラールの向上は、ほんの30~40字の記載ですが、そこにはしっかりとした一次試験の知識が活用されていることをご理解いただけたのではないでしょうか。
まとめ
- 平成20年度第8問設問3を例に解説
- モラールには、内発的動機づけと外発的動機づけにわけられる
- 両者の具体的な内容を過去問を使って整理しておけると、二次試験の特に助言(提案)問題の記述の際にとても使える

中小企業診断士の二次試験勉強に悩む方は多くいらっしゃると思います。それは、一次試験の勉強時から二次試験を本当の意味で見据えた方針を立てられていないことが筆者自身の経験からも言えるのではないかと考えます。
そんな方こそ、一次試験の勉強をしながら、かつ上手に二次試験で活用できる知識を引き出しとしてためておくための具体的提案内容を過去問をもとに整理し、記憶していけると、二次試験の当日には大きな違いが生れています。
中小企業診断士の一次試験の過去問勉強にひと手間加えるだけですので、ぜひ試してみてください。


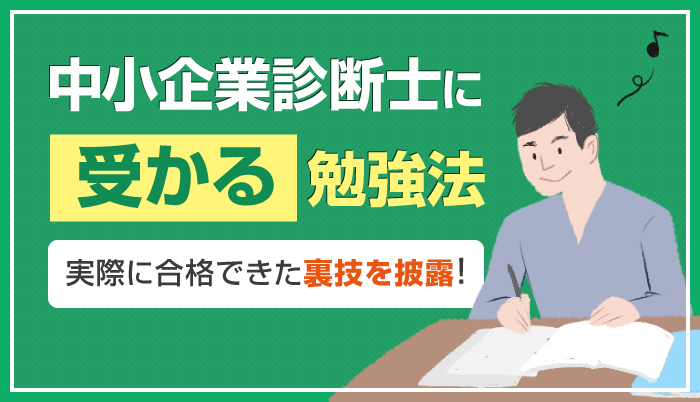















中小企業診断士の一次試験のなかで重要な科目として位置づけられている企業経営理論を勉強中です。二次試験の合格が目標なので、筆記試験にもつながるような一次試験勉強法ってあるのでしょうか。
aerozolさんが、言われている最高の教科書である過去問を活用した方法であると、とても嬉しいです。まじ卍っす。