- 財務・会計の内容をイマイチ理解できていないため、公式をとりあえず暗記してしまおうと考えてしまっている方
- そもそも数字が苦手なため、財務・会計と聞いただけでアレルギー反応を起こしてしまう方
- 最小の努力で最大の効果を得る、中小企業診断士試験の財務・会計の勉強法を身につけたい方
- 筆者の失敗談から公式の丸暗記対応は中小企業診断士の二次試験で歯が立たない可能性が高い〔損益分岐点分析(CVP分析)をもとに解説〕
- 損益分岐点分析〔CVP分析〕の役割をまず理解する
- 損益分岐点分析〔CVP分析〕とは、原価と利益が操業量によってどのように変化するのかを分析するツール
- もっと具体化すると、設備投資などの行動を起こした際に、どのようなコストや利益になるのか最適な意思決定をくだすためのシミュレーション
- 損益分岐点分析CVP分析〕において覚える式はこの1つだけ。
販売単価販売数量=変動費単価生産数量固定費 - この式をベースに中小企業診断士の一次試験の過去問を解くと二次試験への対応力が格段に向上する
金融機関勤めや経理業務をしているなどを除いて、中小企業診断士の試験勉強で初めて財務・会計という科目に触れる方の多くは、科目の特殊性にとまどうのではないでしょうか。
筆者は簿記の借方・貸方でさえ、初めのうちはチンプンカンプンで自分のオツムのなさに頭を抱えたほどです。
ゆえに、中小企業診断士の試験において、財務・会計は受験生の大きな鬼門として立ちはだかります。一次試験そして、二次試験のどちらにおいてもです。
裏を返せば、財務・会計を得意な科目にすることが出来れば、中小企業診断士の試験において、とても大きなアドバンテージを持つことができると言えます。
とは言うものの、財務・会計が難しい科目であることに変わりはありません。しかし、筆者のように財務・会計が苦手だったものでも最終的には得意科目へと押し上げることは可能です。
合格していま振り返った時に、最小の努力で最大の効果を得るために行うべき、ベストな財務・会計の勉強法について、損益分岐点分析〔CVP分析〕をお題に考えてみました。※あくまで筆者の個人的な見解です。
いま振り返って感じる中小企業診断士の試験における筆者の失敗談
筆者は平成27年度に中小企業診断士の試験に合格しました。そして、1次試験は4回、二次試験は6回受験しています。
筆者がなぜ二次試験を6回も受けるハメになってしまったかの原因の1つに財務・会計の計算力のなさが挙げられます。
中小企業診断士の二次試験を見据えた一次試験の勉強がとても重要
まず、筆者の財務・会計における戦歴をご紹介します。結構前の話になりますので、一次試験に関しては、もしかしたら若干まちがっているかもしれないです。おおよそで捉えてください。
| 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一次試験 | 52点 | 72点 | 72点 | 未受験 | 72点 | 未受験 |
| 二次試験 | D | C | C | B | A | A(76点) |
上図から見てお分かりいただける通り、中小企業診断士の一次試験においては点数がとれなくて困ったという想い出はありません。その理由は、とにかく理解の有無はさておいて、公式を覚えておけば、4つの選択肢の中からなんとか正答を探し当てることができるからです。
ただし、一次試験の勉強としては有効ですが、二次試験では役に立つ可能性はとても低いです。また、公式の丸暗記によって実務で使える知識までに引き上げられるかと言われれば、答えはNOです。
衝撃的だったのは、初めて受験した平成22年度の二次試験です。
中小企業診断士の二次試験に初挑戦であった平成22年度で撃沈した事実
財務・会計の勉強当初は嫌悪感があったものの、途中から数字を扱うことにもなれはじめたため、不得意科目までの意識(可もなく不可もなくといった感じです)は持っていませんでした。
そんな中で、迎えた平成22年度の二次試験の財務・会計において、一次・二次ともに頻出論点となっている損益分岐点分析〔CVP分析〕が出題されたのです。
一次試験で覚えた公式をもとに意気揚々と問題を解き始めたら愕然。
損益分岐点分析(CVP分析)なんて朝飯前の問題だと思い、公式をそのまま当てはめようとしたのですが、全く歯が立たたず、試験中に自分の頭の中で試合終了の笛が鳴り響いたことを今でも覚えています。
まだこの時は自分は運が悪かっただけだと意味の分からない勘違いをしていたため、平成24年度の中小企業診断士の二次試験でも損益分岐点分析〔CVP分析〕が出題されましたが、同様のやらかしをすることとなります。
失敗から学ぶべきポイント
- なぜその作業をしているのか、そして一番応用が利くシンプルな算出式は何なのかを考えるようにする癖を常に持つこと
筆者は以下の公式を丸暗記して覚えていました。
損益分岐点売上高=固定費÷(1—変動比率)
これを前提に、以下の二次試験問題を解いてみます。
営業部からの報告によれば、Z社は部品Qの納入価格の20%価格引き下げを要求している。さらにZ社からは、納入価格を現在の価格より30%引き下げることができれば、今後は仕入れ先をD社に一本化し、発注量を2倍にする案が提示されている。部品Qの現在の売上高は2,823百万円、変動費は1,129百万円、固定費は1,640百万円である。
なお、現状の生産能力には十分な余裕があり、生産技術部からは、部品Qの納入量を2倍にしても、その原価構造は現状と変化がないと報告されている。
納入価格を30%引き下げた場合の損益分岐点売上高を求めよ。
引用:中小企業診断士平成22年度第2次試験事例4(財務・会計)第2問(1)改題
先ほどの丸暗記した公式に何も考えずにあてはめていき、
損益分岐点売上高=1,640(固定費)÷(1—1,129÷2,823)(変動比率)
と計算しました。
もちろん間違っているのですが、自分ではどこがどのように間違っているのかさえ気づけなかったのです。
公式を知っているだけではお役立ち度が低いということです。
自分の目も当てられない失敗談をもとに考えると、いろいろな公式の暗記を片っ端から行っていく少し手前で、なぜその作業をしているのか、そして一番応用が利くシンプルな算出式は何なのかを考えるようにする癖を常に持つことがもの凄く重要だと言えます。
損益分岐点分析〔CVP分析〕の役割
中小企業診断士の一次試験は計算問題だけ、かつ選択式なので何とかなりますが、二次試験においては上手くいかないことが分かったところで、損益分岐点分析〔CVP分析〕をなぜ行う必要があるのか、から今一度考えていきましょう。
手順として、まずは中小企業診断士の一次試験の暗記科目で苦労する3文字英語攻略法でご紹介したように3文字英単語を直していきます。
すると、
- Cost(原価)
- Volume(操業量)
- Profit(利益)
となります。
繋げ合わせると、原価と利益が操業量によってどのように変化するのかを分析するツールということになります。
具体的にはどのような時に何の理由で、このツールを使うのでしょうか。
それは、設備投資などの行動を起こした際に、どのようなコストや利益になるのか最適な意思決定をくだすためのシミュレーションをすることです。
中小企業診断士の二次試験の問題をみていただければお分かりになりますが、損益分岐点分析(CVP分析)の問題は、損益計算書や貸借対照表とセットで問題展開されることが鉄板パターンとなっています。
このように一連の流れを捉えるだけで、イメージが生れるため、問題への対応度は格段に変わってきます。
そしてCVP分析で一番重要なのは操業(営業)量の変化によるシミュレーションに着目していることです。
営業量に変化する費用と言えば、売上と変動費ですよね。
- 売上を分解すると
- 変動費を分解すると
売上=販売単価販売数量
売上=変動費単価生産数量
となります。
まとめると、
中小企業診断士の1次試験の過去問(二次試験につながる良問)をチェック
一次試験の勉強だけで見たら、公式を利用して一発で算出する方が良いかもしれません。
しかし、二次試験の対応力を強化するためには、いくつもの公式を暗記するよりもシンプルな計算式を一つ完璧に理解しておくことの方が間違いなく有効です。
なので、算出方法としては若干遠回りをしているのですが、上記の様な計算を行っていくことが中小企業診断士の二次試験の対応力を高めるため、最終合格までの道のりで考えると結果的に近道になります。
上記を踏まえた上で、平成28年度の第2問の問題をチェックしていきます。
次の資料に基づいて、以下の質問に答えよ。
第1期 第2期 期首在庫 0個 10個 生産量 110個 90個 計 110個 100個 販売量 100個 100個 期末在庫 10個 0個 販売単価1,000円、単位当たり変動費600円、1期当たり固定費33,000円
第2期の損益分岐点比率として最も適切なものはどれか。
ア17.5%
イ45.0%
ウ55.0%
エ82.5%
引用:中小企業診断士平成28年度第1次試験財務・会計第8問(2)
- 計算式を当てはめてます。
- 展開します
- Xである販売数量=生産数量を算出します
- 売上高を算出します
- 損益期分岐点比率を出します
1,000(販売単価)X(販売数量)=600X(生産数量)33,000円(固定費)
今回は変動単価が2期とも不変なので、販売数量=生産数量となります。
400X=33,000
X=82.5
1,00082.5=82,500
82,500÷100,000100=82.5%
先ほどの中小企業診断士の平成22年度二次試験をみてみよう
先ほど筆者の中で試験時間中に試合終了の笛が鳴り響いた問題もシンプルな計算式さえ理解できいれば、なんのことはありません。
営業部からの報告によれば、Z社は部品Qの納入価格の20%価格引き下げを要求している。さらにZ社からは、納入価格を現在の価格より30%引き下げることができれば、今後は仕入れ先をD社に一本化し、発注量を2倍にする案が提示されている。部品Qの現在の売上高は2,823百万円、変動費は1,129百万円、固定費は1,640百万円である。
なお、現状の生産能力には十分な余裕があり、生産技術部からは、部品Qの納入量を2倍にしても、その原価構造は現状と変化がないと報告されている。
納入価格を30%引き下げた場合の損益分岐点売上高を求めよ。
引用:中小企業診断士平成22年度第2次試験事例4(財務・会計)第2問(1)改題
- 計算式を当てはめてます。
- 展開します。
- Xを算出します。
- 変動費率を算出します。
- 売上高を算出します。
- 展開します。
- 筆者の失敗談から公式の丸暗記対応は中小企業診断士の二次試験で歯が立たない可能性が高い〔損益分岐点分析(CVP分析)をもとに解説〕
- 損益分岐点分析〔CVP分析〕の役割をまず理解する
- 損益分岐点分析〔CVP分析〕とは、原価と利益が操業量によってどのように変化するのかを分析するツール
- もっと具体化すると、設備投資などの行動を起こした際に、どのようなコストや利益になるのか最適な意思決定をくだすためのシミュレーション
- 損益分岐点分析CVP分析〕において覚える式はこの1つだけ。
販売単価販売数量=変動費単価生産数量固定費 - この式をベースに中小企業診断士の一次試験の過去問を解くと二次試験への対応力が格段に向上する
2,823百万円(既存売上高)0.7(販売単価)2(販売数量)=1,129百万円2(生産数量)1,640円(固定費)X(利益)
3,952.2百万円(売上高)=2,258百万円2(生産数量)1,640百万円(固定費)X(利益)
X=54.2百万円(利益)
1,640百万円(変動費)÷3,952.2百万円(売上高)
この場合は、単価および数量が把握できないため、売上高割合で変動費の率を算出しています
変動比率=0.415
X百万円(売上高)=0.415(変動比率)1,640百万円(固定費)
0.585X百万円(売上高)=1,640百万円(固定費)
X(売上高)=3825.76百万円
よくよく考えてみれば、何も難しい問題ではありませんね。しかし、本質を理解していないと問われ方の角度を変化してきたときに軒並みやられてしまいます。そして、中小企業診断士の二次試験ではこの角度を変えた出題というのは、日常茶飯事です。
ぜひ、各論点の本質を理解することに注力してみてください。
ご参考
ちなみに、二次試験の平成29年度に出題された損益分岐点分析〔CVP分析〕についてこちらで解説していますので、あわせてお読みいただけるとより理解が深まります。
まとめ
参考:あわせて読みたい
中小企業診断士の1次試験合格には過去問研究を徹底にすべし
中小企業診断士を独学で突破するためには、過去問を徹底研究することが一番の近道です。
そのためには、過去問の使い方をまず理解することが必要となります。
筆者の失敗談をもとにした過去問の具体的な使い方について言及しています。
中小企業診断士の1次試験で不得意科目を何とかしなければとお考えの方へ
徹底研究するなかで、中小企業診断士1次試験の苦手な科目をつぶすために厳選に厳選を重ねた有効なおすすめのテキストをご紹介しています。
得意科目をさらに伸ばすよりも、不得意科目を潰す方が合格可能性をグインと押し上げることにつながります。


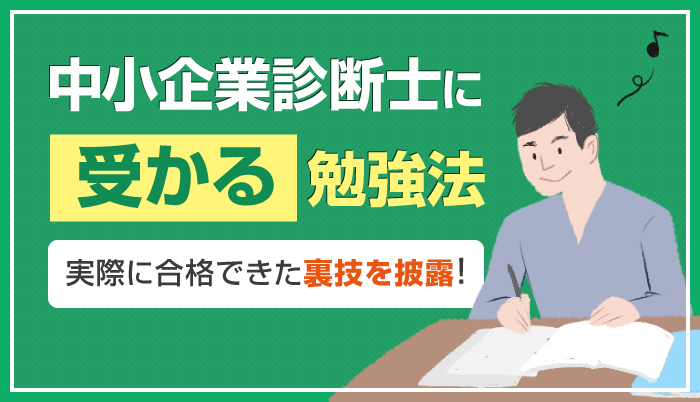







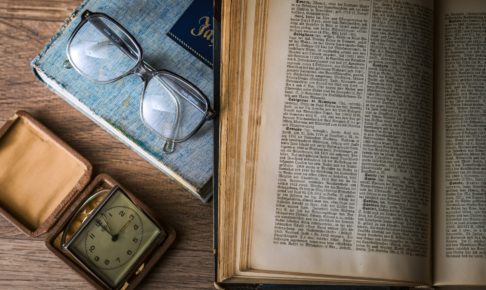











まさしく、今の私のためにある内容でした。一つの公式だけで、一次試験を乗り切り、いま、フリーズしている私のためにある内容でした。ありがとうございます
勇太さま
コメントありがとうございます。
公式を覚えることも重要ですが、なぜその公式が成り立っているのか?過程を理解しようとする意識を持たれると、より理解が深まるかと思います。
意識を変えるだけで、違った世界が見えてくることも多々ありますので、ぜひ導出過程も意識してみてください^^