- 中小企業診断士の1次試験の科目が多すぎて、勉強中の科目以外の復習まで手が回っていない方
- 中小企業診断士1次試験の学んだ科目が増えていった時に、時間対効果の高い復習方法をとりいれたいと思っている方
- 中小企業診断士の1次試験の学んだ科目を久しぶりに復習したら、びっくりするほど内容を覚えていなかった方
最初に、今回の記事の要点をお伝えしておきます。
- 中小企業診断士の一次試験勉強の復習時に陥りやすいわなの全貌をまず知ること
- 導かれる対策は、インプット中の科目:既習科目=2:1の割合で勉強と、限られた時間を最大限有効活用した復習方法の確立
- 具体的には、定期的な復習期間を具体的に数値化すること、時間ではなく論点管理で過去問を中心にした勉強を行うこと
ツイッターで、疑問や質問、リクエストを随時お受付しています。
中小企業診断士試験で知りたい内容あれば、リクエストください!
どこまで実現できるかわかりませんが、鋭意努力して記事化していきます!#中小企業診断士試験 #中小企業診断士 #二次試験 #一次試験も要望があれば #リクエスト情報絶賛募集中— aerozol (@_aerozol) 2017年12月20日
さらに、匿名で質問ができる「質問箱(こちらをクリック)」にも最近登録しましたので、ツイッターアカウントを知られるのが恥ずかしいわという方は、質問箱(こちらをクリック)からご質問ください!
ちなみに、ツイッターのメッセージに送っていただいても構いません。
今回もありがたいことに「スズキアユコさん」から、リクエストをいただきました。
今は毎日情報システム2時間、財務会計50分のペースでやっていますが、だんだん情報システムの予習復習がついていけなくなりつつあります。皿回ししたいのにできないのが悩みです。質問が長くなってすみません💦
— スズキアユコ (@suzuki_ayuko) 2018年2月18日
中小企業診断士の一次試験は7科目もあるため、覚える量が膨大です。初学者の人であれば、新しく触れる科目や初めて聞く単語が多く、混乱してしまう、なんてことがよくあります。
とは言っても、中小企業診断士の一次試験日までの時間は刻々と迫っています。
試験合格、そして取得後の実務において本物の中小企業診断士を目指す熱意ある多くの方が、間違った復習方法によって合格を逃してしまうことを防ぐ対策記事をご紹介します。
中小企業診断士の一次試験勉強の復習時に陥りやすいわな
- 新たな科目のインプットに多大なパワーを使う必要あり
- 既習科目の復習が滞りがち
- 全科目終了後に復習しようとしたら知識がほぼ抜けていて、顔面蒼白
スズキアユコさんが言われているように、中小企業診断士の1次試験は7科目ものボリュームがあります。
初学者の場合は特に注意!
初学者の場合ですと、新しい科目のたびに初めて聞く言葉を理解、そして覚えていかなければなりません。
そのため、一日の時間の使い方として、ほぼ100%とを現在学んでいる科目に使っており、既習科目の復習が滞りがちとなります。
結果、7科目学んだあとに、全科目を復習しようとした際に最初の方の3科目くらい記憶からすっぽり抜け落ちており、もう一度焦って知識を入れ直すパターンは良くみかける中小企業診断士の1次試験の勉強で見かけるあるあるです。
何が間違っているのかを知ることが第一歩
先ほどの陥りやすいわなの全貌を一つずつ見ていくことで、どこの部分の何を改善すべきなのか探っていきます。
新たな科目のインプットに多大なパワーを使う必要あり
新たな科目のインプットに多大なパワーを使う必要があるのは仕方のないことです。むしろ、これを怠ってしまうと、時間対効果が著しく低下するため、新たな科目のインプット(理解)をメインに据えた勉強方針をとることが重要です。
改善ポイント1
しかし、1次試験合格を目標に目指すのであれば、中心に据えつつも、既習科目の勉強も同時に行っていくべきなのは間違いありません。
筆者の中小企業診断士の1次試験を4回受けてきた感覚からだと、一日の勉強時間のうち、インプット中の科目:既習科目=2:1の割合で勉強をこなしていくべきだと断言します。
既習科目の復習が滞りがち
既習科目の復習が滞りがちになってしまう、原因として挙げられるのは、復習に回す時間のなさです。
新たな科目へのインプットにほぼ100%の力を注ぐことによって、既習科目への時間がほとんどさけず、復習がなおざりにされていきます。
全科目終了後に復習しようとしたら、各科目の知識がほぼ抜けて顔面蒼白
改善ポイント2
改善ポイント1で捻出する一日の勉強時間の1割という限られた時間を最大限有効活用した復習方法の確立が必要です。
なお、科目数が増えれば増えるほど、既習科目1つあたりに対する時間割合は減少していく制約条件も踏まえた対策を考えなければならないことも念頭に入れなければなりません。
間違いから導く中小企業診断士一次試験勉強の正しい復習法〔解決策〕
- エビングハウスの忘却曲線を意識した復習
- 定期的な復習期間を具体的に数値化する
- 時間ではなく論点管理
- 過去問中心の勉強法
改善ポイント1は勉強時間の割合を変化させればよいだけですので、できていない方は意識して勉強を行いましょう。
効率的な復習勉強法をどうやって確立させるかが、大きな焦点となります。
エビングハウスの忘却曲線
復習に関する勉強法の解決策に入る前に、人間の特性に関する大事な事実をお伝えします。この特性を理解したうえで、復習を計画的にこなしていくことが短期的な記憶から長期的な記憶へと効果的に変化していきます。
よく言いふらされている理論ですが、重要な内容なのでご紹介します。

学習してそのまま放置した場合に、人間はどのくらい記憶しているかを表しています。これを見ると、1ヶ月後には約8割も忘れるという衝撃的な結果がでています。
つまり、全科目終えた後に一気に復習をしようとしたときに記憶が頭からすっぽり抜けてしまうのは、とても自然なのです。
記憶したことを忘れていないのであれば、そんなあなたは超人以外のなにものでもありません。凡人とはレベルが違うとしか言えないですね。

一方で、学習後に復習を定期的に行った場合、上図の通り、1か月後でも約9割も学習内容を記憶できています。これを長期記憶と言います。この状態にまで持っていければ、安定的な得点を獲得できるようになります。
定期的な復習期間を具体的に数値化する
定期的な復習が重要なことは理解したら、次に発生する疑問はじゃあどのくらいの頻度で復習すればよいのかです。筆者がとりいれていた勉強方法をお伝えします。参考程度にご覧ください。
唐突ですが、2つのキャッチコピーをみて、どちらの方が信頼できるキャッチでしょうか。
どちらが信用できるかと言えば、その2ですよね。
違いは、数字が奇数か偶数かだけです。これは、人間は本質的に奇数を受け入れやすいという特性を持っており、キャッチコピーによく用いられる手法です。
この性質を活かして、以下を復習ペースのベースとしていました。
| 当日 | 2日後 | 3日後 | 4日後 | 5日後 | 6日後 | 7日後 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 復習日 |
時間ではなく論点管理
先ほどのエビングハウスの忘却曲線からも分かるように、既習科目にどれだけ毎日触れることができるかが、各科目の覚えた内容を長期記憶に変えられるかにかかっています。
なおかつ一日の勉強時間の1割で、既習科目に毎日触れるには全ての科目でつまみ食い復習を行うほかありません。
企業経営理論は30分勉強したや財務・会計を1時間勉強したといった時間での管理は満足感は得られますが、どこまで何を復習するのか目的をもっての勉強が難しいです(記録として、勉強時間をつけるのは筆者も大賛成です)。
そのため、論点別の管理で勉強の進捗管理を把握していくのが一番有効な手立てとなります。
過去問中心の勉強法
論点別の管理で進捗管理を把握していく際に、勉強の主軸に据えるべきは、中小企業診断士の本試験問題として出題された過去問につきます。
過去問の重要性、具体的な使い方については、こちらをお読みください。
中小企業診断士を独学で突破するためには、過去問を徹底研究することが一番の近道です。
そのためには、過去問の使い方をまず理解することが必要となります。
筆者の失敗談をもとにした過去問の具体的な使い方について言及しています。
もっと具体的に過去問の勉強方法を知りたい、過去問を解いたが全然歯が立たない、そもそも使い方がわからないといった方におすすめです。
中小企業診断士の一次試験の科目を使って説明
運営管理と財務・会計が終了し、企業経営理論を現在勉強中で一日にとれる勉強時間が3時間だと仮定します。その際に、どのような復習方法をとればよいのかご説明していきます。
勉強時間の割合
まず勉強時間の割合は以下のようになります。
| 企業経営理論 | 財務・会計 | 運営管理 | |
|---|---|---|---|
| 勉強時間 | 2時間 | 30分 | 30分 |
注目してほしいのは、財務・会計と運営管理の時間です。ともに30分しかありません。そのため、何を学ぶかを明確にしなければなりません。
時間ではなく論点管理
そこで重要なのは、先ほどもお蔦した通り、論点管理です。それでは、運営管理(生産管理)の過去問(論点別)の一部を使って具体的にみていきます。
| 当日 | 2日後 | 3日後 | 4日後 | 5日後 | 6日後 | 7日後 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生産管理の基礎 | |||||||
| 工場立地とレイアウト | |||||||
| 製品開発・製品設計 | |||||||
| 設計技術 | |||||||
| ライン生産 | |||||||
| セル生産 | |||||||
| 管理方式 |
これでいくと、3日後に復習する論点が2つ、7日後に論点が3つに増えています。一見、論点が増えていく一方のに30分の時間だけで対応できないと感じる方もいらしゃるかもしれません。
過去問勉強法を愚直にこなしていけば、経験曲線効果が必ず発揮されるため、1論点にかける時間は回が増すごとに必ず減少していきます。
これを繰り返していくことで、最終的には7科目の復習を1日で行えるようになりますので、ご安心ください。中堅大学卒の筆者でもできるのですから。
重要なことは、時間ではなく論点での管理が徹底できるか、そして過去問と心中するほど気持ちをもって勉強をやりぬことができるかです。
まとめ
- 中小企業診断士の一次試験勉強の復習時に陥りやすいわなの全貌をまず知ること
- 導かれる対策は、インプット中の科目:既習科目=2:1の割合で勉強と、限られた時間を最大限有効活用した復習方法の確立
- 具体的には、定期的な復習期間を具体的に数値化すること、時間ではなく論点管理で過去問を中心にした勉強を行うこと


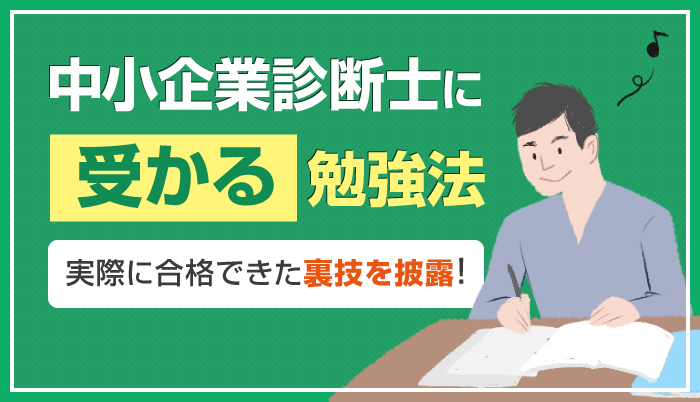

















同じような境遇の方により多くお伝えするためシェア いただけると嬉しいです!