中小企業診断士の二次試験は国語の試験なのか
以前、ご紹介した中小企業診断士は何者かで詳細を述べた通り、中小企業診断士として国が求める能力は「経営課題に対応する診断・助言」
です。
筆者はここをよく理解しておらず、中小企業診断士の二次試験を6回も受けるハメになってしまいました。経営課題がとても重要だと気付くまでの5回は、巷で言われているように中小企業診断士の二次試験は国語の試験だと完全に思い込んでいたからです。そのため、小・中学生で習った助詞や助動詞といった使い方などを勉強したりもしました。初めて受けた時には、AABDの総合Bであったのに対し受験するごとに評価は下がっていき、5回目にはなんとCCCCの総合Cまで落ちました。
振り返ってみると、表面上のことに気を取られすぎていて、本当に必要な事例企業を成長させるためのストーリーを描こうとしておらず、すみからすみまで与件文をしっかりと読めていたと思っていたつもりが、実は全く読めていなかったことを痛感しました。5回目の評価を受けた時点で、ようやく自分が勉強してきた方向性は大きく間違っていたことに愕然としたことを今でも覚えています。筆者の経験として中小企業診断士の一次試験を突破されている時点で、国語の能力は問題ないと言えます。それよりも、中小企業診断士として与件文を読めていない方が圧倒的に多いです。
結論
確かに国語の試験という側面もありますが、さほど重要ではありません。それよりも、筆者のような現象が発生してしまう多くは、中小企業診断士の二次試験に対する具体的な与件文の読み方を知らないがために、間違った努力となってしまっているのではないかと思います。
では、中小企業診断士の二次試験を突破するためにどうすればよいのか
中小企業診断士の二次試験は国語試験であるものの、似て非なるもの。だからと言って、経営課題の把握と一口にいってもよくわからないと思いますので、これから具体的にどのように与件文を読んでいけばよいのかについて、今後、筆者が中小企業診断士の二次試験に合格した平成27年度までの過去問を使ってお伝えします。
中小企業診断士二次試験の平成24年度事例Ⅱを参考に
今回はその触りを、中小企業診断士の二次試験の平成24年度事例Ⅱを使ってお伝えします。※なお、直近2年間の二次試験問題はみていないので、準備が整い次第となります。
経営課題の意味とは
その前に、経営課題という言葉について、どのように定義されているかを見てみたいと思います。経営課題は複合語であるため、分解すると「経営」と「課題」となります。「経営」については、言わずもがななのであえて説明しませんが、「課題」についてはネット(コトバンク)で調べてみると以下のように記載されていました。解決しなければならない問題。果たすべき仕事。
となっています。
つまり、経営課題とは、会社全体として最優先で解決しなければならない問題や果たすべき仕事といえそうです。
今後の経営課題
全文を記載することは蛇足となるので省略し、着目すべき部分に絞ってお伝えします。分かりやすいところからいくと、今後の経営課題です。
他方で、新規顧客の開拓が進まないという問題がある。Bメガネのなじみの客が伝道者として新顧客を紹介してくれるケースも徐々に少なくなってきている。売上高はほぼ横ばいである。ロードサイドに立地している地方都市の店舗と比較して、首都圏に立地する店舗は、いずれも売場面積が狭く、フレームの品揃えは限定的である。また、勤続年数の長い従業員は、ファッションや流行には強い関心を持っておらず、若い従業員は少ない。
このブロックでは、新規顧客の開拓が進まないという会社全体として解決しなければ問題がはっきりと出ています。おそらく、中小企業診断士の二次試験を受験されるようなレベルの高い皆さんは気づかれたと思います。
その要因は、(1)Bメガネのなじみの客が伝道者として新顧客を紹介してくれるケースの減少、(2)フレームの品揃えは限定的、(3)勤続年数の長い従業員は、ファッションや流行には強い関心を持っておらず、若い従業員は少ない、の3つだということも分かります。これを各設問で解決していくこととなります。
それでは、次のブロックについて見てみましょう。
このような状況下、昨年、眼鏡一式を低価格で販売しており、テレビで広告を打っているディスカウント型Mメガネ・チェーンがBメガネの本店の第1次商圏内に出店する計画があることが分かった。そこで、Bメガネの社長は、中小企業診断士であるあたなに診断と助言を求めてきた。あなたは、Mメガネ・チェーンと競合する地方都市の店舗で店長および従業員にヒアリング調査をするとともに、その店舗を愛顧する数名の顧客に対してグループインタビューも実施した。その結果、価格に魅力を感じてMメガネ・チェーンで購入したが、不満を持った消費者がいることが分かってきた。
Bメガネ店舗を愛顧する顧客なのに、Mメガネ・チェーンで購入する人が存在しているという驚きの事実が見て取れます。また、不満をもった消費者がいると書かれていますが、裏を返すと不満を持たずにそのままBメガネからMメガネ・チェーンへと流れてしまった元愛顧客がいると推測できそうです。
この経営課題を読み取れているかどうかが、与件文をしっかりと読み取れているかどうかの大きなポイントであると筆者は考えています。最後の一文は、はっきりとうたわれているわけではないので、気づく人にしか気づきません。筆者がこの一文を見て気づけたのは、推察力や論理的思考力がとても高いからではありません。それは、このブロックよりも以前に見落としてはならないポイントを押さえているからというだけなのです。
私のムダな経験が中小企業診断士の二次試験を独学合格目指す皆様に、少しでもお役にたてていれば幸いです。


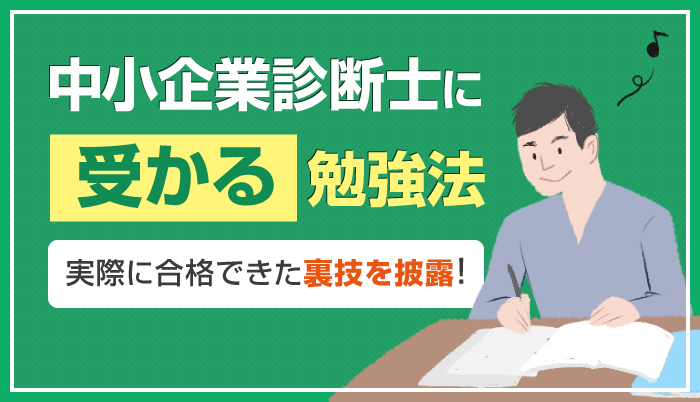












同じような境遇の方により多くお伝えするためシェア いただけると嬉しいです!