中小企業診断士を独学で突破するためには、過去問を徹底研究することが一番の近道です。そのためには、過去問の使い方をまず理解することが必要となります。
本記事は過去問を徹底研究するなかで、中小企業診断士1次試験の苦手な科目をつぶすために厳選に厳選を重ねたおすすめのテキスト(参考書)をご紹介していきます。
過去問の研究がまだ進んでいない方は、まずこちらをお読みください。
また、中小企業診断士試験の最短合格のための勉強法をまだ知らない方は、まずこちらをお読みください。
中小企業診断士の独学合格を目指すためにテキストよりも前に読んでおくべき書籍
中小企業診断士の独学合格のために必要な勉強ノウハウが書かれた書籍「非常識合格法」(中小企業診断士の専門学校クレアールから資料請求〔無料〕するとタダで貰えます)は読んでおくべきです。
科目別テキストの紹介の前に紹介した理由は、中小企業診断士の試験突破で一番重要な過去問の勉強ノウハウが惜しみなく書かれているため、各科目の知識を習得するよりも重要な内容だからです。
最短合格に確実につながる1冊なので、資料請求【無料】して効率よく情報収集しましょう。
※資料請求フォームの備考欄に「非常識合格法プレゼント応募」と記入しないと貰えないのでご注意ください。
資料請求(無料)で短期合格ノウハウ本を無料で貰うならこちらから
中小企業診断士の一次試験におすすめのテキスト(参考書)を科目別にご紹介
経済学・経済政策〔初日|1限目の科目〕
中小企業診断士1次試験の中で、経済学・経済政策を苦手の科目とする方は、財務・会計についで多い印象にあります。
しかし、経済学・経済政策は基礎を理解できると途端に得点が急上昇する科目でもあります。
予備校で市販されている教科書だけでは理解できない部分が多々あり
中小企業診断士の予備校代表格であるTACさんのスピードテキストはとても分かりやすいテキストなのですが、経済学・経済政策に限ってはページ数の都合上なのか必要な説明が多々省かれています。そのため理屈よりも暗記で対応せざる得ない局面に出くわしました。
経済学・経済政策は、中小企業診断士の一次試験のなかで理解重視科目に分類されるため、暗記では角度を変えられた問題を出されてしまうと対処できません。
省かれてしまった部分の説明を補ってくれるおすすめのテキスト(参考書)は石川先生の速習シリーズです。
ポイント1〔高校生でも理解できるやさしい解説〕
グラフや図表がてんこもりに使われているので、視覚的にとても分かり易いです。また、数式などを極力使用しない説明には、ほれぼれしてしまほどです。
なおかつ、先ほど述べたTACさんのスピードテキスト(参考書)のようにページ数の都合上カットされたと思われる本当は理解しておいた方が得点につながる説明がしっかりとなされています。
さらに、中小企業診断士の1次試験も考慮に入れたテキスト作りとなっているので、試験範囲と完全にマッチしています。
ちなみに、出版時期が2011年と少し古いですが、経済学は学問であるため新しかろうが古かろうが大して影響はなく、さらに、基礎的な知識をみにつけるのならばなおさら心配する必要はありません。
ポイント2〔無料で動画がみれる〕
なんと、な・な・なんと、テキスト(参考書)だけでなく動画でも学ぶことができます。
しかも無料でみれるというのは、独学者にとって何とも嬉しい限りですね。
一度全て目を通した後に、復習と理解促進を図る補助的な役割として動画を活用するのがおすすめの使い方です。
購入をおすすめする方
- マクロ経済学・ミクロ経済学の初歩的な部分ですでにつまづいてしまった
- 力技の暗記対応に不安しか覚えない
- マクロ経済学・ミクロ経済学の理屈をしっかりと理解し、暗記量を減らしたい
といった方には、間違いなく買いの一冊です。
[itemlink post_id=”8058″] [itemlink post_id=”8059″]財務・会計〔初日|2限目の科目〕におすすめ
中小企業診断士の1次試験の科目のなかで、受験者が一番苦手にしがちな科目として、財務・会計はトップオブザトップです。
原因として、計算量が圧倒的に足りないことが挙げられます。
ポイント〔問題の多さ〕
計算量が圧倒的に足りない理由として、過去問を10年分こなしても1つ1つの分野は年度で追ってみると、多くて2、3問といったところです。つまり、各論点でこなせる最大でも30問程度となります。
財務・会計は、解き方を理解し反射的にこなせるほどのが必要となるため、いろいろな問題に触れることが重要です。
この差を補ってくれるのが、TACさんが販売している集中特訓財務・会計計算問題集なのです。
購入をおすすめする方
- 過去問だけではなんか物足りないと感じている
- 過去問以外の問題を解くことで、対応力を強化したい
といった方には、時間対効果が高いものとなるはずです。
運営管理〔初日|3限目の科目〕におすすめ
運営管理は生産管理と店舗運営管理の2つの論点に大きく分かれます。
このうち店舗運営管理は、小売業など生活に密着した内容を問われる科目なので、多くの皆様はとっつきやすく、とても面白い科目だと感じるはずです。
一方で、生産管理においては、実際に製造業で働いている方でないとなかなかイメージしずらい科目となっているのではないかと容易に想像します。筆者も製造業での勤務経験があるわけではないので、フライス盤ってなんのこと?というだけでなく、ジャストインタイムシステムって初耳だし、名前長くないですか・・と思っていました。
しかも、市販されている教科書は経済学・経済政策でも述べた通り、図解などをふんだんに利用することはページ数の都合上、難しいことが、生産管理という科目をとっつきにくくしている最大の問題です。
ポイント1〔図解で説明してくれているのでイメージしやすい〕
初心者向けに、しかも予備知識がゼロの方をターゲットにした内容となっています。なぜなら、図解をのせてくれているだけでなく、著書が言葉をかみ砕いて説明してくれているので、とてもイメージがわきやすくなります。
これによって、生産管理の理解促進の妨げとなっていたイメージのわきにくさを払しょくできるため、市販の教科書を読み返すと爆速的に理解度が深くなります。
ポイント2〔著者が中小企業診断士〕
なんと、この本を書いていらっしゃる著者は中小企業診断士の先生です。そのためか、中小企業診断士の1次試験の範囲と相関性がバリバリ高く、試験用に執筆されたのかと思うほどです。
筆者が知っていたのは、こんなにおしゃれなカバーじゃなかった気がするけどな・・・と調べたところ、2017年11月に再版がかかっていたようです。
ビジネス書でさらに専門書に近い分野の書籍が再版がかかることはなかなか珍しいことから、この本は根強い人気があったのだと筆者も驚きました。
以外と知られていない、中小企業診断士の生産管理を理解するのにとても役立つのが、[ポイント図解]生産管理の基本が面白いほどわかる本です。
購入をおすすめする方
- 製造業に勤務しているわけではないので、イメージがわかず勉強が進まない
- 生産管理の大枠を掴んだうえで、中小企業診断士の教科書を読みこんでいきたい
- 中小企業診断士の二次試験にもつながる知識をいれておきたい
といった方には、激押しの1冊です。
[itemlink post_id=”8158″]
企業経営理論〔初日|4限目の科目〕におすすめ
すみません。
皆様の勉強効率を高めるテキスト(参考書)という視点で、休日に本屋に出向いていろいろと探してみましたが、存在しませんでした。
読み者としてであればおすすめできる書籍は沢山あるのですが、中小企業診断士の1次試験の苦手な科目をつぶすためにと考えた場合、企業経営理論に限っては過去問を徹底的に当たったほうが良いと考えます。
社会人向けにビジネススクールを運営するグロービスさんが、経営戦略、マーケティングに加え、PM理論やエンパワーメントなどの組織論を動画で分かり易く解説してくれています。
なんと、お試し期間として無料で7日間視聴ができます。理解を深めるツールとして活用ください。
※無料会員登録時にクレジットカード情報の入力と利用プランを選択するため、7日間の無料体験経過後は、選択したプラン料金が発生します。
経営情報システム〔2日目|1限目の科目〕におすすめ
生産管理同様に、経営情報システムもなじみのない方にとっては、非常につらい科目です。
筆者は働き始める前までは、パソコンなんてほとんど触ったことのない人種でした。
そんな人とっては、経営情報システムは未知の世界すぎて、オトモダチニなれそうにないかもという気分になってしまうと思います。
なぜ、このようなことが起こってしまうのかは、毎度の繰り返しになりますが、市販のテキスト(参考書)はページ数の都合上、より詳細な説明が割愛されてしまう傾向にあるからです。
ポイント〔ITパスポート試験の内容は中小企業診断士1次試験と相関性が高い〕
中小企業診断士の1次試験は様々な検定科目2級程度の難易度の寄せ集めでできています。具体的に知りたい方は、こちらをご覧ください。
IPAが実施するITパスポートは、経営情報システムの基礎的な知識を問う試験です。この基礎的な知識という部分が中小企業診断士の1次試験との適合度がMAXなのです。ご参考までに、ITパスポートの趣旨を以下に挙げておきます。
ITを利活用するすべての社会人・学生が備えておくべきITに関する基礎的な知識が証明できる国家試験です。
具体的には、経営戦略、マーケティング、財務、法務など経営全般に関する知識をはじめ、セキュリティ、ネットワークなどのITの知識、プロジェクトマネジメントの知識など幅広い分野の総合的知識を問う試験です。
ITパスポート用に作られているテキスト(参考書)を利用したほうが、説明が詳しく記載されているので理解が進むはずです。
正直、ITパスポートのテキスト(参考書)であればどれでも大差ありませんが、図解が多く使われていた書籍を一つご紹介しておきます。
購入をおすすめする方
- ITはからっきし苦手で拒否反応を示してしまう
- 教科書のに書いてある経営情報システムの内容を覚えたのに過去問の点数が思わしくない
といった方にはおすすめです。
[itemlink post_id=”8060″]経営法務〔2日目|2限目の科目〕におすすめ
ポイント〔実務家が語る経験をもとにした説明がリアルに感じられるため、記憶に残りやすい〕
経営法務の頻出論点のなかでも会社法はMVP的論点です。
会社法は最終的には暗記になりますが、法律が成立するには裏側には色々な背景がひそんでいます。
歴史を覚えるときも、無理やり暗記するのと、背景や一連のストーリーを理解した上で暗記するのでは、頭に刻まれる印象度がまるで違ってきます。
それと同じように会社法務を実務とする著者の経験をもとに実務上のポイントなども織り交ぜながら、だけど初心者に分かりやすい平易な言葉で軽妙に説明してくれてるので、会社法が身近に感じられるはずです。
購入をおすすめする方
- 会社法を力技で暗記しようとしたが、やっぱり無理で挫折しそう
- 暗記系科目といえども、理解を進めたうえで暗記に入りたい
といった方にはおすすめです。
中小企業診断士の二次試験におすすめのテキスト(参考書)
中小企業診断士の2次試験においても、なるべく早くから開始したいとお考えの方は、こちらもご覧ください。
まとめ
あくまで、過去問の徹底研究が一番重要です。
その中で、ご自身が苦手だと感じる科目の補強する意味合いでご紹介したおすすめのテキスト(参考書)を利用してもらえればと思います。
もう一度いいますが、あくまで過去問の徹底研究が合格を目指すうえでは、一番重要です。


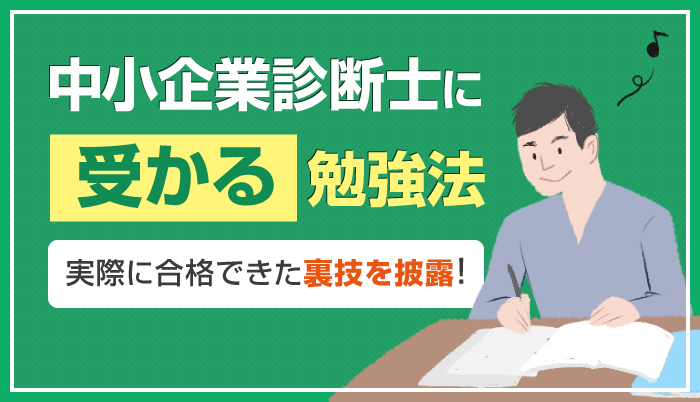







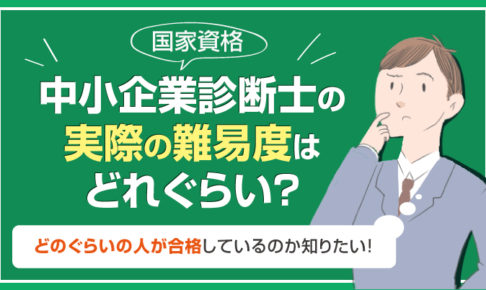






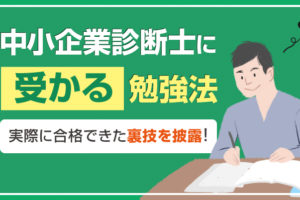






同じような境遇の方により多くお伝えするためシェア いただけると嬉しいです!